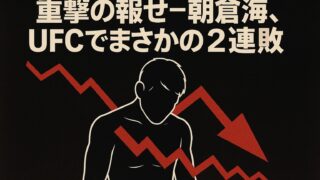「食事とがん」は無関係ではない
食事とがんの関係はしばしば誤解されがちです。ひと皿、ひと口がすぐにがんの原因になるわけではありませんが、長い時間軸で見れば「何をどれだけ、どのように食べ続けるか」は、確かにがんのリスクに影響します。世界的な研究レビューでも、体重や食事、飲酒、運動といった生活習慣が、いくつかのがんの発症リスクに関係することが示されています。ここでは、最新の知見に基づいてポイントを整理し、明日から実践できるヒントに落とし込みます。
まず押さえたい全体像:因果ではなく「確率」を動かす
食事が決めるのは「なる・ならない」のスイッチというより、確率の上下です。リスクを大きく上げる行動を避け、下げる行動を積み重ねることが、将来の自分への投資になります。巷で語られる「これさえ食べれば防げる」という単純化や、「○○は絶対にダメ」という極端な主張には注意が必要です。科学的にわかっていることと、まだ議論が続いていることを区別する姿勢が、結局いちばんの近道です。
リスクを上げる食習慣
- 過度の飲酒:飲酒は複数のがんに関連します。可能なら量を減らし、飲まない日をつくるのが賢明です。
- 加工肉・赤身肉のとり過ぎ:ソーセージ、ベーコン、ハムなどの加工肉は、食べる頻度と量に応じてリスクが上がることが示されています。牛・豚などの赤身肉も、量が多いほど注意が必要です。
- 高塩分:塩分のとり過ぎは、胃の健康に負担をかけます。漬物、加工食品、外食の汁まで飲み干す習慣は見直してみましょう。
- 焦げ・高温調理:肉や魚を強い火で焦がすと、望ましくない化合物が生じます。香ばしさと焦げは別物。焼き過ぎには要注意です。
- 過体重・肥満:体脂肪が増えること自体が、いくつかのがんのリスク上昇と関係します。「何を食べるか」と同じくらい「どれだけ食べるか」も大切です。
リスクを下げる方向に働く食習慣
- 野菜・果物・豆類・全粒穀物:食物繊維や多様な微量成分が、腸内環境を整え、長い目で見た体の防御力を支えます。とくに全粒穀物と食物繊維は大腸の健康と好相性です。
- 健康的な脂質:オリーブオイル、ナッツ、青魚などに含まれる脂質は、過剰摂取を避けつつ賢く使うと食事満足度も上がります。
- 適度なコーヒー:コーヒーは一部のがんのリスク低下と関連する可能性が示されています。ただし砂糖やクリームたっぷりでは逆効果です。
- 無糖飲料・水を基本に:清涼飲料の常飲は過体重につながりやすく、巡り巡ってリスクを押し上げます。喉の渇きには水を。
サプリは「補う」もの。万能ではない
サプリメントは不足を補う道具であって、がん予防の魔法ではありません。特定の栄養素を高用量でとることが、かえって健康を損なう可能性も指摘されています。基本は食事から。医師の管理下で必要な場合に限ってサプリを活用する、が原則です。
よくある疑問に答えます
Q. 糖質や甘いものは「がんのエサ」だから絶対NG?
体は糖を主要なエネルギーとして使います。甘いものを少し食べたからがんになる、という話ではありません。ただし、過剰な糖分は体重増加や代謝の乱れを招き、間接的にリスクを上げます。極端なゼロか百かではなく、総量を整える意識が現実的です。
Q. 乳製品は避けるべき?
乳製品は栄養源としての側面があり、大腸の健康にプラスに働く可能性が指摘されています。一方で、がん種によっては影響が異なるとの研究もあります。量とバランスを意識し、自分の体調や目標に合わせて選びましょう。
Q. お茶やサプリの「ポリフェノール」で予防できる?
特定成分を単独でとって明確に予防できる、という結論は限定的です。日々の食事全体の質を高めるほうが、トータルでのメリットは確かです。
実践のコツ:今日からできる5つの行動
- 主食は精製度の低いもの(玄米・全粒パン・オートミールなど)を選ぶ回数を増やす
- 野菜は「両手いっぱい」を目安に、色の違うものを組み合わせる
- 加工肉は「日常」ではなく「たまの楽しみ」に位置づける
- 家での調理は「中火・短時間・蒸す・煮る」を基本に、焦げ目は控えめに
- お酒は量と頻度を見直し、休肝日をつくる
相対リスクと絶対リスクを理解する
ニュースで「○○でリスクが○%上昇」と聞くと不安になりますが、それが元の確率のどれくらいの話なのか(絶対リスク)を考えることが大切です。冷静に数字を読み、総合的な生活習慣の改善に注力しましょう。
個人差と医療者への相談
基礎疾患、治療中の病気、アレルギー、文化的背景、価値観によって、適した食事は変わります。がんの治療中・治療後の方は、とくに主治医や専門職(管理栄養士)と相談して、自分に合った食事計画を立てることが重要です。
まとめ:完璧より「続けられる良い習慣」を
食事とがんは「無関係ではない」が、恐れるより賢く付き合う対象です。極端な方法に飛びつくのではなく、科学的に確からしい方向へ舵を切り、続けられる工夫を積み重ねる。今日の小さな一歩が、未来の大きな安心につながります。