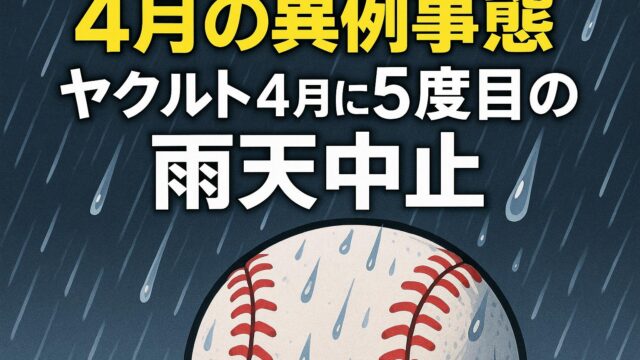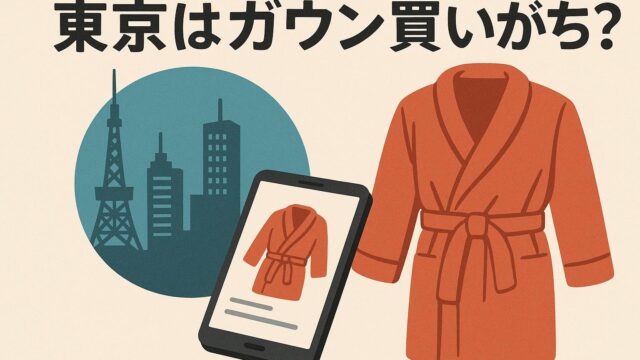日本の海でいま何が起きているのか
日本の漁獲量がこの数十年で大きく落ち込み、およそ40年で約3分の1まで縮小したという指摘が広がっています。サンマやサケ、スルメイカなど、かつて「旬の味」として親しまれてきた魚の不漁が続き、現場の疲弊、価格の変動、食文化への影響が重なって見えてきました。識者は、資源の持続可能性と産業の再設計を同時に進める必要があると警鐘を鳴らします。
漁獲量減少の背景:ひとつの原因に還元しない
1. 海の環境変化
海水温の上昇や海流の変動、プランクトン組成の変化は、魚の回遊や成長、産卵に影響します。たとえば、サンマの来遊域が沖合に移り、沿岸での漁が難しくなるといった現象が報告されています。海そのものが「生産性の地図」を書き換えつつあるのです。
2. 資源管理の難しさ
魚種ごとに資源量の変動が大きく、自然の周期性と人為的な影響が絡み合います。沿岸・沖合・公海や、国境を越える回遊資源など、管理単位も多層的。捕る量(TAC)、網の目合い、休漁、産卵期の保護などの対策は進んできましたが、科学的助言の精度や遵守の徹底、関係国との協調など、改善余地はまだあります。
3. 現場の負担増
燃料価格の高止まり、氷や資材のコスト上昇、船や港の老朽化、人手不足と高齢化。収入が不安定な中で投資や世代交代が難しく、漁に出るほど経済的に厳しいケースも生まれます。価値づくりより量に依存してきた構造は、資源が細るほどさらに苦しくなる負の連鎖を招きます。
食卓と地域に広がる影響
漁獲量の減少は、店頭価格や入荷量の不安定化につながり、外食・中食のメニュー構成や、家庭の「いつもの魚」を揺さぶります。輸入への依存度が上がれば、為替や海外需給の影響も受けやすくなります。一方で、地域では「獲る漁業」から「価値をつくる漁業」への転換に挑む動きが拡大。未利用魚の活用、鮮度保持や急速凍結による品質の平準化、ブランド化や観光との連携など、量に頼らず稼ぐ工夫が芽吹いています。
海と産業を守るためのロードマップ
1. 科学にもとづく「長く獲り続ける」管理へ
- 中長期の資源評価に基づくTACや禁漁期・禁漁区の運用強化
- 漁獲データのデジタル化・リアルタイム共有による合意形成の迅速化
- 生態系ベース管理(EAFM)で獲る魚だけでなく海のつながりを守る
2. 現場の生産性と安全性を底上げ
- 省エネ型の操業・機器更新への投資支援と共用インフラの整備
- 若手・移住者・副業人材の参入を促す柔軟な働き方と技能認証
- 港-市場-物流のコールドチェーン最適化と品質評価の標準化
3. 価値づくりと市場の信頼
- MSCやASC、国産の認証表示の普及とトレーサビリティの徹底
- 未利用魚や小型魚のレシピ開発、学校給食・外食との連携
- データに基づく価格形成(サイズ・脂質・鮮度などの可視化)
私たちにできる3つの行動
- 旬と産地を意識して買う:季節ごとの多様な魚を選び、偏りを減らす
- 認証・表示をチェック:資源と環境に配慮した選択で現場を後押し
- 地域の魚食文化を支える:地場の鮮魚店や直売、加工品を生活に組み込む
消費は「小さな投票」です。日々の選択が、漁法や資源管理、地域の雇用を変えていきます。
希望の芽はすでにある
定置網でのサイズ選別や混獲低減の工夫、藻場・干潟の再生、AIや衛星データを使った来遊予測、未利用魚のプロダクト化、観光と組み合わせた体験型の販売。各地で生まれている実践は、海の変化に適応しながら価値を高める具体策です。重要なのは、競争ではなく「学び合い」。うまくいった知見を水平展開し、海の回復力(レジリエンス)を産業の回復力につなげることです。
「たくさん獲る」から「長く獲り続ける」へ
漁獲量の減少は、ひとつの時代の終わりを告げているのではなく、新しいやり方への合図です。海の変化を前提に、科学・技術・地域の知恵を束ね、価値で稼ぎ、資源を回復させる。その道は遠回りに見えて、じつは最短です。私たちの食卓を未来につなぐために、いま選べる行動から始めましょう。