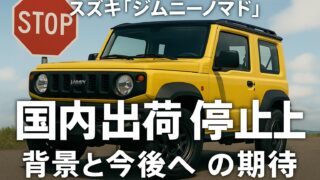遺産9500万円 弁護士が配分せずか
―信頼を預けた先で起きた「遺産トラブル」と向き合う
遺産相続という言葉は、私たちの生活において比較的遠い存在のように感じられることもあります。しかし、いざその立場になったとき、予想外のトラブルや感情のもつれが生じることも少なくありません。今回は、遺産総額9500万円にも及ぶ遺産の配分を任された弁護士が、依頼者家族に対して遺産を分配していなかったという報道に注目し、なぜこのような問題が起きたのか、そして私たちがそこから何を学べるのかを考えてみたいと思います。
報道によると、この遺産配分トラブルの発端は、ある家庭の父親が亡くなったことによって発生しました。亡くなられた父親には遺産があり、その配分を第三者の専門家、つまり弁護士に依頼して手続きを進めてもらうことになりました。ところが、遺族側の証言によれば、その弁護士から本来支払われるはずの遺産が長らく分配されず、不信感が募っていたというのです。
信頼のはずが、トラブルの火種に
弁護士という職業は、私たち市民からすれば非常に信頼性の高い専門職です。法律の知識が豊富で、厳格な倫理規定のもとに職務を遂行し、依頼者の利益を守るべき存在。そのような存在に大切な遺産の配分を任せることは、ごく自然な対応だったはずです。
しかし、今回のケースのように、その「信頼」が裏切られたと感じてしまうような事態が起きてしまうと、当事者にとってその心理的なショックは非常に大きいものとなります。遺産というものは単なる「お金」ではなく、故人の人生の積み重ねであり、残された家族への「思い」でもあります。
報道によれば、遺族は長い間、弁護士に説明を求めていたものの、納得のいく返答が得られなかったとされています。その結果、遺族は弁護士会に対して懲戒請求を申し立てるという非常に重い決断を下しました。
弁護士への懲戒請求とは?
弁護士に不正や不当な行為があった場合、一般市民でも所属の弁護士会に懲戒請求を行うことが可能です。これは、弁護士という公共性の高い職業が社会的な信頼の上に成り立っていることを示しており、その信頼が損なわれかねない状況があった場合に対処できるようにするための仕組みでもあります。
懲戒請求があった場合、その内容は弁護士会内に設けられた綱紀委員会や懲戒委員会によって調査され、必要に応じて処分が課されます。処分の内容は戒告、業務停止、退会命令、除名などがあり、その重さは内容によって大きく異なります。
今回の報道における弁護士がどのような処分を受けることになるのか、あるいは説明責任を果たすことができるのかは、今後の推移を見守る必要があります。
なぜ遺産トラブルが増えているのか?
実は、今回のような遺産を巡るトラブルはここ数年で大きく増加傾向にあると言われています。その背景にはいくつかの社会的事情があります。
まず一つ目に、高齢社会の進展が挙げられます。日本では高齢者が増加しており、自然と相続の件数も増加しています。それに伴って、相続に関する法律や制度の理解が不十分なまま手続きを進めてトラブルになるケースが多くなっているのです。
二つ目に、家庭の形が多様化してきたという点があります。例えば、再婚をして新たに家庭を持ったり、子供同士の関係が複雑だったりすると、遺産の分配に対する解釈や期待が異なりやすくなります。
そして三つ目は、相続財産の管理を専門家に依頼するケースが増えたことで、逆にその専門家による不適切な対応が問題になる事例が表面化してきているという点です。多忙な中で対応が雑になった、あるいはそもそも信頼に値しない人物が専門家として活動していたなど、原因はさまざまですが、いずれにしても大きな問題です。
私たちが学ぶべき「対処法」
では、こういったトラブルを回避するためにはどのような対策があるのでしょうか?以下にいくつかの重要なポイントを紹介します。
1. 複数の専門家の意見を聞く
遺産の整理や配分について一人の弁護士や司法書士に頼り切るのではなく、場合によっては複数の専門家に相談することでリスクを減らすことができます。セカンドオピニオンのように、知識や経験が異なる専門家の意見を聞くのはとても有効です。
2. 重要なやり取りは書面で残す
口頭の約束や説明は、のちに「言った言わない」の争いになりがちです。可能な限り、契約書や委任状、説明書類などを文書で残しておくことで、自分の立場を明確に証明することができます。
3. 定期的な進捗確認を行う
手続きが一度依頼された後、すべてを専門家に任せっぱなしにせず、定期的に進捗を確認することも大切です。トラブルが表面化する前に、早期に気付くことができる可能性があります。
4. 弁護士会や公的相談窓口の利用
万が一、不審に感じた場合は、弁護士会などの公的な相談窓口に早めに問い合わせることも一つの手段です。少しでも不安を感じたら放置せず、第三者の視点でのアドバイスを求めましょう。
信頼に足る専門家との繋がりが重要
遺産というセンシティブな問題を扱うには、何よりも「信頼」が欠かせません。特に弁護士や税理士、司法書士などの専門家を選ぶ際には、過去の評判や対応力、そして説明責任への姿勢などをよく確認する必要があります。
また、すべてを専門家任せにするのではなく、家族同士で事前に話し合いをしておくことも、後々のトラブル防止に役立ちます。たとえば人生の終盤にさしかかる親が、自ら意思表示をして「この財産はこう分けてほしい」などと明確な意向を示すことで、残された家族が混乱するリスクを減らすことができます。
まとめ:誰もが直面する可能性のある「相続」だからこそ
今回の報道は、遺産を巡るトラブルが他人事ではないことを私たちに教えてくれました。高額な遺産であるかどうかにかかわらず、誰にでも起こりうる問題であり、準備や対応を怠ると想像以上に大きな影響を家族に与えてしまうこともあります。
法律や制度、そして人間関係や信頼といった要素が複雑に絡み合う相続の世界では、知識を持ち、冷静に対応することが必要です。信頼できる専門家との関係を適切に築き、家族同士で定期的に話し合いを持つことで、今回のようなトラブルを未然に防ぐことができるはずです。
遺産とは、亡き人が残した大切な「心の財産」でもあります。その価値を最大限に生かすために、私たち一人ひとりが賢明な選択をしていきたいものです。