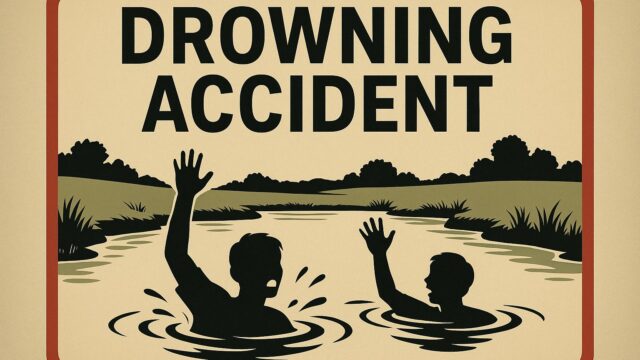日本の食卓を支える農業は、私たちの暮らしにとって欠かせない基盤のひとつです。広大な土地と比較的冷涼な気候を活かして、全国有数の農産地として知られる北海道。しかし、近年この北海道で、農家を継ぐ子どもの数が急激に減少しているという衝撃的な事実が明らかになりました。
報道によると、ここ10年で北海道における農業後継者はおよそ4割も減少したといいます。この数字は単なる統計ではなく、日本の農業の未来を大きく左右する警鐘とも言えるでしょう。
この記事では、なぜ農業の後継者が減少しているのか、その要因を整理するとともに、私たち一人一人ができることについても考えていきたいと思います。
北海道農業の現状と課題
農業王国とも称される北海道は、米・小麦・ジャガイモ・てんさい・乳製品など多様な農産物の生産が盛んで、日本国内はもとより海外への輸出も積極的に行われています。特に大規模農業が可能な土地柄もあり、機械化やスマート農業への取り組みも進められています。
しかしその一方で、深刻な課題も抱えています。その筆頭が「担い手不足」や「後継者問題」です。農家の高齢化が進む中、次の世代が農業を引き継がなければ、いくら技術が進歩しても農業の持続は困難です。今回、10年で後継者数が約4割減少したというのは、まさにこの問題が現実として表れた結果だといえるでしょう。
後継者が減る背景には何があるのか?
農業の後継者が減っている背景には、いくつかの複合的な要因があります。
1. 経済的な安定性への不安
農業という職業は、天候や市場価格などの不確実性に常に影響される仕事です。農作物が豊作でも値崩れすれば収入に結びつかず、不作の場合は赤字になってしまうことも。安定した収入が見込みにくいという点で、若者にとって魅力を感じにくい職業とも言えるでしょう。
2. 都市への人口流出
高等教育機関や職業選択の幅が広い都市部へ若者が向かうことで、農村地域に若者が残る割合が年々減っています。北海道でも、札幌を除く地方ではこの傾向が顕著です。結果として、実家が農家であっても帰って継ぐ選択をしない、あるいはできない状況が続いています。
3. 農業に対するイメージ
「きつい」「汚れる」「休みが少ない」など、古くからの農業に対するネガティブなイメージがあることも要因です。最近ではスマート農業やICT活用といった新しい形も登場していますが、それが十分に浸透しておらず、依然として「つらい仕事」という先入観が残っています。
4. 親の負担と世代間ギャップ
農家を引き継ぐということは、単に仕事を受け継ぐだけでなく、経営そのものを承継するという重みがあります。土地・設備・地域との関係性など、目に見えない責任も多く、家庭内での引き継ぎがスムーズにいかないといったケースもあります。そうした家族内の葛藤も若者が農業を敬遠する一因となっています。
後継者不足の影響は地域だけにとどまらない
農家の減少は、単に農業者が減るというだけでなく、地域社会や私たちの食の安全にも影響を及ぼします。
まず、農村地域の経済や文化が次第に衰退していくという問題があります。農業が基幹産業である地域にとって、農家の減少は雇用・商業・学校・交通など様々な面に影響を与えます。また、耕作放棄地が増えることで、景観の悪化や動物被害の増加、生態系への影響も懸念されます。
さらに、食料自給率の低下も深刻な課題です。日本の食料自給率はすでに低い水準で推移しており、国内での安定した生産基盤が脆弱になることで、価格の高騰や輸入依存のリスクが増していきます。北海道は日本の食を支える要の地域であり、そこで農家が減るということは、私たちの日々の食卓にも直結する問題なのです。
求められる支援と新しいアプローチ
このような状況に対して、さまざまな取り組みが始まっています。
たとえば、国や自治体では若者の就農支援策として、研修制度や資金援助、農地の確保支援など多方面でのサポートを行っています。また、農業高校や農業大学校などの教育機関では、次世代を担う技術者や経営者を育成するためのカリキュラムが充実してきています。
さらに注目されているのが、ICTやAIを活用したスマート農業です。ドローンによる害虫管理、AIによる作物の生育予測、センサーによる水管理など、従来のイメージから離れた先進的な農業のかたちが今、少しずつ広がりを見せています。これにより、若者が農業に対して持つ印象が変化し始めているとも言われています。
また、地域外からの新規就農者を積極的に受け入れる取り組みも見られるようになりました。移住希望者への住居支援やコミュニティの形成支援など、地域ぐるみで新しい“家族”を迎え入れる取り組みも広がりつつあります。
私たちにできることは何か?
農業の後継者問題は、決して農家や地域だけの問題ではありません。私たち一人ひとりの暮らしと密接に結びついているのです。
では、私たち消費者には何ができるのでしょうか?
第一に意識したいのは「地元の食材を選ぶ」ということです。地産地消の習慣を持つことで、地域農業の支援につながります。スーパーで産地を見て北海道産の野菜を選ぶ、地域の直売所や物産展で買い物をすることも、立派な貢献となります。
また、農業に関する情報や現場の声に耳を傾けることも大切です。SNSやYouTubeでは、農家の日常や課題を発信している若手農業者も増えています。そういった発信に触れることで、農業がより身近になり、関心も深まるはずです。
さらに、家族や学校で子どもたちに農業の大切さを伝えていくことも、長い目で見た支援となります。未来の職業としての「農業」が魅力ある選択肢になっていくために、今からできることはたくさんあります。
まとめ:北海道から見える日本農業の未来
後継者の著しい減少という北海道の農業が直面する厳しい現実は、日本全体に共通する課題です。しかし同時に、そこから立ち上がろうとする若手農業者や地域の挑戦、技術や支援制度の進化には希望も感じられます。
農業の未来は、農家だけのものではなく、私たち消費者、地域、そして社会全体が一緒に支えていくものです。北海道での現象を「自分ごと」として捉え、食と農のつながりに改めて目を向けてみることから始めていきませんか。