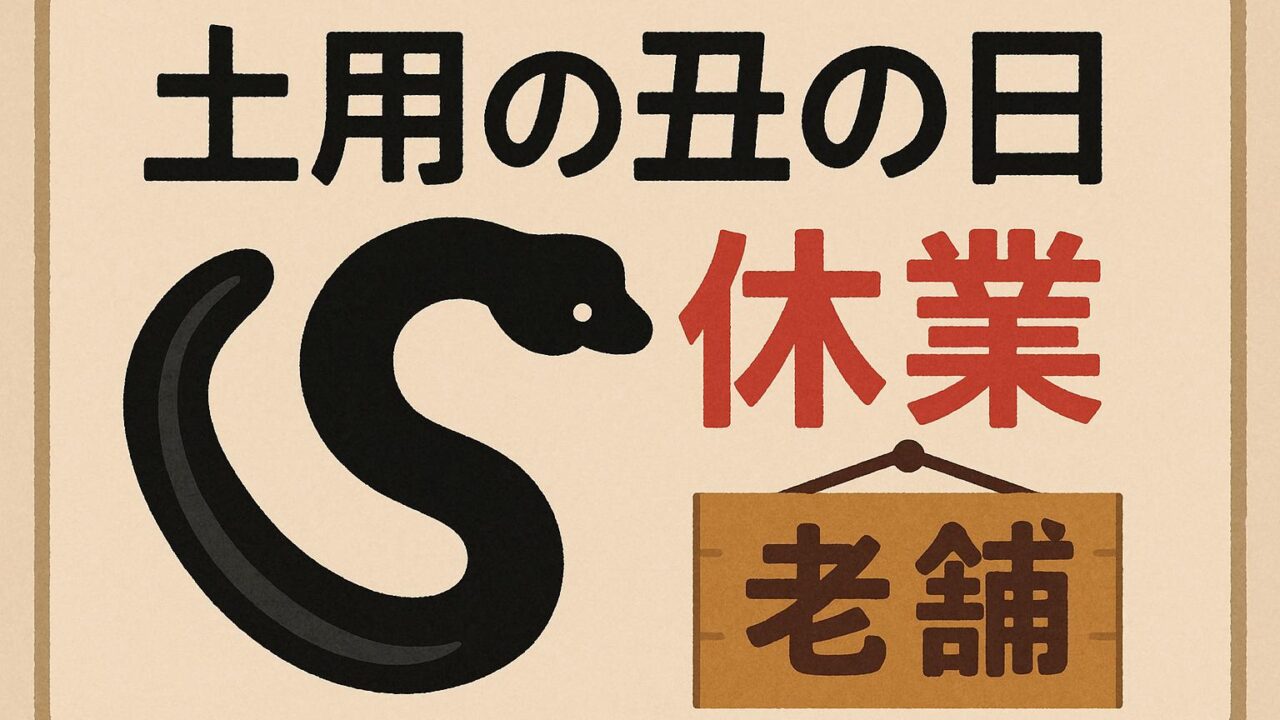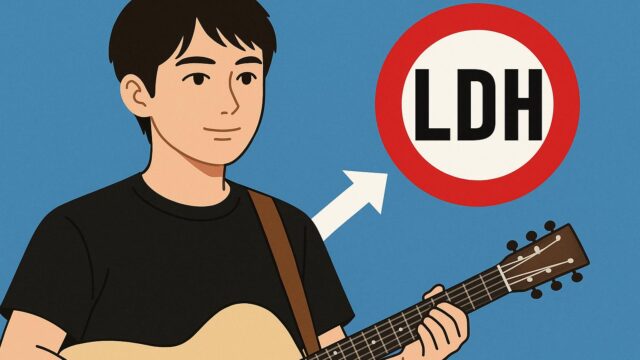土用の丑の日——あえて休む老舗の選択に見る、日本の文化と商いの心
日本の夏の風物詩の一つに、土用の丑の日にうなぎを食べるという習慣があります。コンビニエンスストアから老舗料亭まで、うなぎが夏の販促商品の筆頭として登場するこの時期、多くの飲食店が特別メニューやキャンペーンで賑わいを見せます。
そんな中、その土用の丑の日に“あえて店を休む”老舗うなぎ屋があるというニュースが注目されています。繁忙期の真っ只中での店休。それはただの企業戦略ではなく、伝統や職人の誇り、そして食文化への深い洞察に根ざした選択でもあります。
今回は、この「あえて休む」という老舗の決断に焦点をあて、日本が誇る食文化と、それを支える人々の美学について紐解いてみます。
土用の丑の日とウナギの由来
まず、なぜ土用の丑の日にうなぎを食べる習慣が生まれたのかを簡単におさらいしましょう。
“土用”とは、立春・立夏・立秋・立冬の前およそ18日間を指し、季節の変わり目を表す言葉です。そして“丑の日”は、十二支の中の一つで、暦から導かれた特定の日を示します。つまり“土用の丑の日”とは、夏の季節の変わり目にあたる期間内で“丑”に該当する日のことです。
この土用の丑に“う”のつくものを食べると夏バテしないという言い伝えがあり、当初は梅干しや瓜なども候補でしたが、「うなぎ」が定着した背景として、江戸時代に蘭学者の平賀源内が、うなぎ屋に「本日丑の日」と告知するよう進言したことが一説として語り継がれています。
現代では、夏バテ対策としてうなぎの栄養が認識され、この日に合わせて多くの人がうなぎを求めるようになりました。
繁忙期にあえて休む老舗、その真意とは
土用の丑の日こそ、うなぎの需要が最も高まる日。通常なら販売促進に力を入れたい日ですが、その日に営業をあえて休む老舗の選択には、深い哲学があります。
ニュースで紹介された東京・千住の老舗「尾花」は、創業から100年以上という長い歴史を持ちながら、この繁忙期に毎年定休日を貫いています。その理由について、「うなぎという食材の特性」と「職人の手仕事の限界」が語られています。
まず、うなぎは非常にデリケートな食材です。大量生産や保存・流通が難しく、品質のばらつきが課題となります。特に夏場は養殖場での飼育にも影響が出やすく、需給バランスの乱れが仕入れ価格や品質に直結します。職人にとって何よりも大切なのは、「味を落とさず、妥協しないこと」。無理な仕入れや過剰な注文に応じるより、通常営業での質を保とうとするその姿勢は、まさに“商い”という言葉の真意、「飽きない」に繋がります。
また、ベテラン職人による手作業が中心の老舗うなぎ屋では、土用の丑のような特需に対応するために、短期間で大量の注文をこなすことが困難です。品質を落とさず、心を込めた一皿を提供するには、一日にできる量が限られており、それを超えるオペレーションは根本的に“らしさ”を損なってしまうリスクがあります。
つまり彼らにとって、土用の丑の日は“最も重要な日”であると同時に、“最も提供の質が揺らぐ可能性がある日”でもあるのです。
伝統と信頼を守るという選択
顧客の期待が高まる中、それをあえて裏切るように見える選択は、ブランド力が無ければできない判断です。しかし、「尾花」のような老舗には、確かな味とともに、長年にわたって積み上げてきた信頼があります。短期的な売上ではなく、日々の誠実な営業を積み重ねることで、“特別な日に来てもらわなくても、いつ来ても同じうなぎが味わえる”という安心感を提供しているのです。
さらに、“一番良い状態のうなぎを食べてもらいたい”という真摯な姿勢は、結果的に顧客からの「誠実さ」として伝わります。多くの人々が利益優先の社会で効率を求める中、このように「変わらないこと」の価値が再認識され、多くの支持を集める要因となっています。
「一膳のうなぎ」に込められた職人の魂
うなぎという料理は、ただ焼いて出すものではありません。生きたうなぎを割き、串を打ち、白焼きにし、蒸して、再びタレで焼く。一連の工程はすべて職人の技術であり、目利き、火加減、タレの塩梅まですべてが味に影響を与えるといいます。
特に、関東風のうなぎは、蒸しの工程によってふわっとした口当たりが実現されるため、この蒸し加減の妙もまた、熟練の技を必要とします。
この経験と技術の蓄積が、老舗の「味」を作っています。つまり、老舗の味は「時間」でできていると言っても過言ではありません。その積み重ねを守るために“休む”という選択は、現代における職人のあり方として、非常に示唆的です。
「休む」という文化と労働観
今回の事例からもう一つ注目すべき点は、「休む」ことの意味です。現代社会では、特に飲食業を含むサービス業で“休む”ことが美徳とされない風潮もありますが、「本当に良いものを提供するには、休養も必要だ」と明確な意思を持つ企業や職人たちの価値観が、新しい働き方、生き方のお手本ともなり得ます。
無理をしてまで儲けることが果たして持続的かどうか。短期的な成功よりも、長期的な信頼や調和を価値とする考え方は、私たちが心豊かな生活を営む上で、重要なヒントを与えてくれます。
最後に
土用の丑の日という特別な日に、あえて店を閉めるという英断。それは、伝統を守り、質を重んじる姿勢の表れであり、日本人が大切にしてきた「おもてなし」や「まごころ」の体現です。
このようなニュースは、単なる飲食店の営業方針を超え、日本文化の奥深さや、物事に込められた意味を考える良いきっかけになります。大量生産・大量消費の時代に、あえて立ち止まり、「本当に良いもの」を守り続けるその姿勢に、私たちはあらためて敬意を持ちたいものです。
「老舗とは、時間と誠実さでできている」——そう思わせてくれる、この小さな“休業”から、多くのことを学び取れるのではないでしょうか。