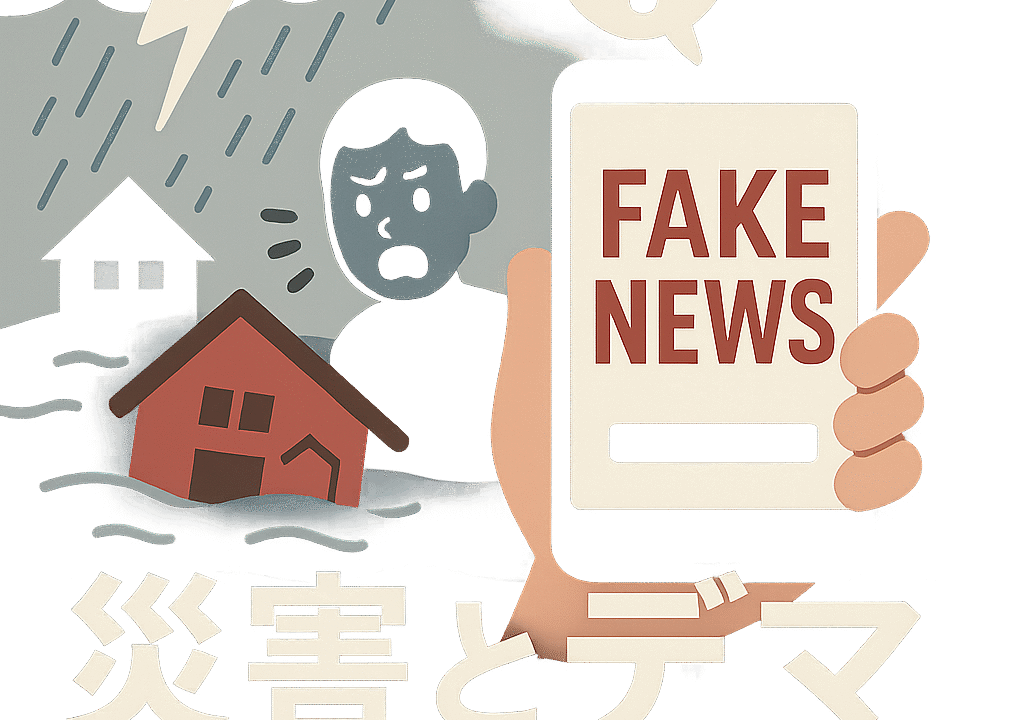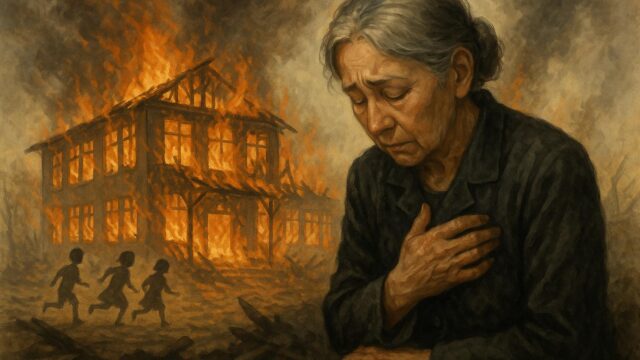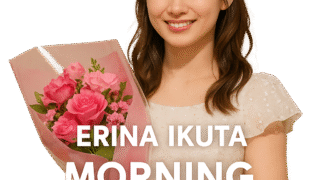近年、私たちが直面する自然災害の頻度や規模は驚くほど増加しており、それに伴い、情報の重要性もかつてないほど高まっています。正確で迅速な情報共有は、災害発生時の冷静な判断や的確な避難行動に直結し、多くの人々の命や生活を守る鍵となります。
しかし情報の拡散が速くなる一方で、正確性に欠けたデマやフェイクニュースも瞬く間に広まり、人々を混乱させてしまうという重大な問題も起きています。特にSNSやインターネット上では、悪意ある投稿や誤解を招く内容があっという間に拡散され、結果として現場の支援や行政対応にまで悪影響を与えています。
今回は、徳島県や鳥取県で起きた「大災害デマ」騒動を通じて、現代社会における情報との向き合い方について考えてみたいと思います。
災害発生時、混乱のなかで飛び交う根拠のない情報
情報元によると、複数の都道府県にまたがり豪雨や河川の氾濫などが発生した後、SNS上では「大きな被害が出ている」「地域一帯が水没した」「死者が多数出ている」といった、事実関係が未確認の情報が急速に拡散しました。そのなかには明らかに虚偽と判明した情報も含まれており、特に徳島県や鳥取県の被災地の状況について、大きく誤解を招く内容が投稿されていました。
こうしたデマ情報は、状況を正しく把握しようとする一般市民、被災者、さらには安否を気遣う家族や友人に不安を与えるだけでなく、救助や支援活動を行う公的機関やボランティアの活動にも深刻な影響を及ぼします。事実、一部では消防や警察が、SNS上の虚偽情報をもとに問い合わせに追われ、本来の活動に支障をきたした例も報告されています。
なぜ災害時にデマが広まるのか?
災害時、誰もが状況の確認に不安を抱えるなか、早く情報を得たいという思いから、目にしたニュースやSNS投稿をすぐに共有してしまうことは容易に想像できます。そして、「誰かが言っているから」「知人からの情報だから」とソースをきちんと確認せずに拡散してしまうということが往々にして起こり得ます。
また、近年では加工された動画や写真も容易に作成され、あたかもリアルな被害を映し出しているかのような投稿が注目を集め、勝手に信憑性が高いものとして拡散されてしまうケースもあります。こういった偽情報は、発信者が悪意を持っている場合もあれば、単なる誤解や勘違いによる発信というケースもあり、その見極めが一般ユーザーには難しいのも現状です。
情報を受け取る側の責任と心構え
災害が発生したとき、正しい情報を得たいのは誰しも同じです。その一方で、SNSやネット上の情報は玉石混交で、信頼性を適切に見極める目が必要とされています。特に以下のようなポイントに注意することで、私たち自身がデマの拡散者になることを防ぐことができます。
1. 情報の出所を確認する
「この情報はどこから来ているのか?」を必ず確認しましょう。信頼できる公的機関や報道機関の情報なのか、あるいは個人の憶測なのかを見極めることが大切です。
2. 拡散する前に内容の真偽を確かめる
たとえ投稿が感情的で、助けを求めているように見えても、その情報が本当に必要な支援を求めているのか、すでに解決済みの過去の事例ではないかなど、冷静にチェックすることが重要です。
3. 写真や動画を鵜呑みにしない
写真や映像があったとしても、出所不明なものや過去の災害の時の画像が使いまわされている可能性もあります。そうした点にも警戒しましょう。
4. 不安を煽る情報には注意する
「もう終わりだ!」「あの地域は全滅した」というような極端な表現が使われている投稿は、冷静に判断することが求められます。過剰に不安を煽る情報ほど、シェア欲が高まる傾向にあるため、あえて距離を置く姿勢が大切です。
地域や家族を守るために私たちができること
災害情報に対する誤解や混乱を少しでも減らすために、私たちができることは想像以上に多くあります。地域の防災訓練に積極的に参加したり、日頃から正しい情報源にアクセスする習慣をつけておくことも大切です。
また、多くの自治体では、災害時に市民に向けて発信される緊急情報がLINE・メール・アプリなどで受け取れるサービスを提供しています。こうした公式なサービスを活用することで、情報の正確性を高めることができます。
もしSNSなどで、誤った情報やミスリードにつながる投稿を見つけたとしても、それに対して過剰に反応するのではなく、落ち着いてスルーする、あるいは正しい情報を伝える投稿をする、という冷静な対応が求められます。
また、家庭内での情報リテラシー向上も重要です。高齢者や子どもたちは災害時ほどいつも以上に不安を感じやすく、デマに踊らされる可能性も高まります。家族全体で話し合い、情報をどこから得るべきか共有することも、支え合うために不可欠です。
これからの私たちに求められる「情報防災」
災害が私たちの暮らしに影響を及ぼすことは避けられない現実ですが、「情報による二次災害」は防ぐことができます。嘘の情報や誇張された投稿が無防備に拡散されることを防ぐためには、私たち一人ひとりが”情報の送り手”でもあり”受け手”でもあることを自覚し、語られる内容とその背景を冷静に見極める力を養うことが求められます。
被災地への誤報は、ある種の傷痕となって人々の心に残ります。正しい支援が届くべき場所に届かない、新たな不安と混乱が次々に生まれる。そのような事態を少しでも減らせるよう、ネット社会に生きる私たちが今一度、情報との向き合い方について真剣に向き合うことが必要です。
大切なのは、事実を知る目と、正しく伝える意志。そして、誰かの声を真摯に受け止める心です。情報が命を守る時代に生きる私たちは、単に発信するのではなく、共に支え合う力として情報を使っていくことが、今後一層求められていくのではないでしょうか。
今回の「大災害デマ」騒動を通して得た教訓を、ぜひこれからの防災意識の向上に役立てていきましょう。