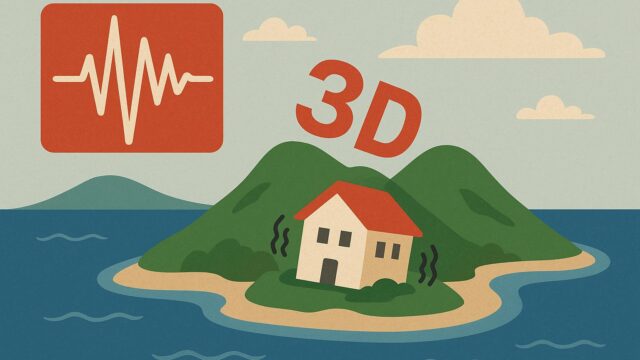「諦めた私立進学 無償化に冷めた目」
近年、日本では教育の無償化をめぐる議論が様々な場面で行われています。特に、高校無償化の範囲を私立高校にも広げるという方針が打ち出されたことにより、多くの国民の関心が集まりました。経済的な理由で進学を断念せざるをえなかった家庭にとっては大きな希望であり、また、子育て支援の一環としても注目される施策です。
しかし、この「私立高校授業料の実質無償化」について、現実にその恩恵をフルに受けられる家庭や生徒は一部に限られているという声が少なくありません。特に、制度開始以前に経済的な理由から進学を断念した家庭や、生徒の進路選択に直結した最も重要な時期をすでに過ぎてしまった家庭にとっては、「今さら感」が否めず、期待と失望が入り交じる複雑な感情が募っています。
この記事では、実際に私立高校進学を断念した家庭、現行制度の対象外となった家庭、そして今後に期待をかける家庭の想いを通じて、「私立高校授業料実質無償化」の現状と課題について見ていきます。
■ 無償化を待てなかった子どもたち
大阪府の一家庭、母子家庭で育てられた中学3年生の娘を持つ母親・大谷さん(仮名)は、私立高校への進学を「泣く泣く」諦めました。娘さんの成績は良く、志望していた私立校には合格の可能性が十分ありましたが、授業料や学費、通学費用などを考えると「経済的に無理」と判断せざるをえなかったと言います。
まさにその後、国および自治体から「私立高校の授業料無償化」が段階的に拡充されるという発表が相次ぎました。しかし、かつてその支援を必要としていた家庭にとっては既に手遅れで、進学先の選択肢は狭まり、その機会は二度と戻ってきません。
大谷さんは、「喜ばしい制度ではあるけれど、子どもの人生を左右する大事な進路選択にとって半年程度のずれでも間に合わない。支援がもっと早ければ、選択肢は違った」と話しています。
■ 「実質無償化」の限界
私立高校の授業料無償化は、「年収約910万円未満」など、世帯収入に応じて支援の対象となる仕組みです。加えて、都道府県ごとの予算や施策が関わるため、支援の枠組みは地域によって異なります。
その結果、例えば居住地によっては十分な無償化が受けられるのに対し、他地域の同じ年収帯の家庭では支援が限定的であるという不公平感も生まれています。
さらに、「授業料の無償化」といっても、諸費用や教材費、制服代、遠足や行事の費用などは対象外です。進学後の保護者負担は依然として大きく、多くの家庭にとっては、「無償化」という言葉から期待されるほどの効果は実感しにくいという実態があるのです。
■ なぜ私立高校進学が望まれるのか
公立高校と私立高校の違いについて、地域や学校ごとで様々な特色がありますが、中には、専門的な教育カリキュラムや独自の進路指導体制、多様なクラブ活動や課外学習などが充実している私立高校も多く存在します。
保護者や生徒が私立校に進学を希望する最大の理由は、「子どもに合った教育環境を選びたい」という想いにあります。選択肢の幅を持たせることは、個々の資質を伸ばす上でも大変意義のあることです。
それだけに、経済的な理由でその選択肢が奪われることへの悔しさや、制度による公平性の欠如に対する不満を抱く声は少なくありません。
■ 過去を救う制度にはなりにくい
教育制度の改革には時間がかかるものです。制度を設計し、国会を通し、予算を確保し、地方自治体と連携しながら展開していくには時間が必要です。ただし、その間にも、毎年数十万人の中学卒業生が進学先を選び、人生の分岐点に立たされるのが現実です。
ある教育関係者は、「制度は常に未来に向けた施策で、過去に対応することは難しい」と語ります。それこそが、今の高校生たちやその保護者が制度改正に抱く“冷めた目”の背景にあります。
また、施行前の子ども達が制度の対象外であることによる“教育格差”が事後的に拡大してしまう危険性も否定できません。
■ 今だからこそ問われる「公平性」と「一貫性」
子育て支援、特に教育に関する支援制度について問われるべきは、「公平性」と「一貫性」です。
対象となる年代や地域が限定されることで、隣同士の家庭でも支援を受けられるかどうかが異なれば、社会的な信頼の低下にもつながりかねません。また、一時的な景気対策としての支援ではなく、将来にわたって制度が継続されるという「安心感」も必要です。
制度の不平等に敏感なのは、保護者だけではなく、将来を担う子どもたち自身です。ある高校生が「兄は無償化の対象外。自分は対象。なんだか申し訳ない」と語るように、兄弟間での制度格差という形で家庭にも波紋は広がります。
■ 教育の機会均等を本当の意味で実現するには
公教育の原点のひとつは、「機会の平等」を提供することです。どんな家庭に生まれても、自らの努力や意志で未来を切り開ける社会。それを目指すためには、経済的なハードルが進路の選択肢を奪うことのないようにする必要があります。
そのためには、制度の細やかな設計はもちろんのこと、制度導入のスピードや情報の周知徹底、過渡期における特例措置など柔軟な対応も求められます。さらに、授業料以外の負担も含めた包括的な支援のあり方が問われているのです。
■ 未来への期待と願い
現在進行形で制度の恩恵を受けられる子どもたちがいることは事実であり、教育無償化が着実に前進していることもまた確かです。しかし、社会全体が一体となって応援する姿勢がなければ、制度本来の効果は薄れてしまいます。
教育とは、未来への投資です。そして、投資の成果はすぐには現れません。それでも、すべての子どもたちが“自分らしく生きる”ための道を選べるような社会こそが、これからの日本に求められる姿ではないでしょうか。
制度の隙間に取り残されることのないきめ細やかな支援を、多くの声と共に広げていくことが今、求められています。教育は、誰か一部の特権ではなく、すべての子どもたちの権利であることを改めて胸に刻みたいものです。