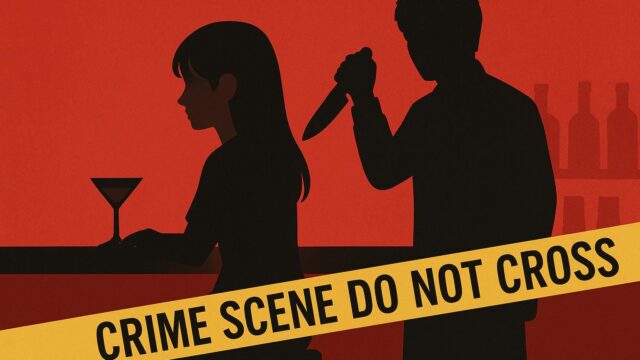2024年夏のボーナス、大企業の平均支給額が過去最高に
~ 景気動向や労働環境への影響を探る ~
2024年の夏のボーナス(賞与)支給が本格化する中、公益財団法人日本経済研究センターが発表した最新の調査によると、大企業の一人当たりの平均支給額は99万1,207円と、過去最高額を更新しました。この金額は前年同期比で3.1%の増加となり、これまで最も高かった1997年の98万8,472円を上回る水準となりました。
この記事では、大企業夏の賞与が過去最高を記録した背景や、賞与の増加がどのように経済全体や労働環境に影響を与えているのかを詳しく解説し、中小企業や非正規労働者への波及効果、そして私たちの生活に与える意味についても考察していきます。
■ 賞与支給額の上昇、その背景とは
賞与支給額の過去最高記録には、いくつかの要因が絡んでいます。
まず第一に、堅調な企業業績があります。日本の主な輸出企業や製造業では、原材料高や人件費の上昇に直面しながらも、生産性改善や販売戦略の見直しによって利益を維持・拡大。その結果、社員への還元として賞与を増額する企業が多く見られました。特に自動車、電機、インフラ企業などが支給額の上昇をけん引しています。
加えて、人材確保の競争もあります。近年、若年層の労働力が減少しており、企業は優秀な人材の流出を防ぐためにも待遇の改善を余儀なくされています。賞与は、その中でも従業員満足度を左右する重要な要素の一つであり、採用活動や定着率に直接関わるものです。
さらに、マクロ経済の視点から見ても、日本経済はコロナ禍からの回復基調にあり、民間消費や投資が持ち直している状況です。そのため企業にとっても長引く節約よりは、従業員のモチベーション向上や消費活性化を後押しする意味で、賞与の増額が“攻めの経営”として歓迎されています。
■ 製造業が高水準をけん引、全体を押し上げ
今回の調査では、特に製造業のボーナスが全体の平均を大きく押し上げていることが分かっています。製造業は前年同期比で4.0%増加し、平均支給額が100万円を超えました(101万8,614円)。世界的な半導体需要や電気自動車の市場拡大などが、日本の大手製造業に追い風になっており、それが各企業の業績好調へとつながりました。
一方、非製造業も1.6%増とプラス傾向ではあるものの、支給額や伸び率は依然として製造業に比べると控えめです。特にサービス業においては、依然として人手不足や仕入れコスト上昇の影響で利益率が圧迫されており、賞与へ大きく還元できない企業も少なからずあるようです。
■ 中小企業との格差も顕在化
大企業における夏賞与の大幅な増加は大きなインパクトを持ちますが、その一方で中小企業との格差も顕著となっています。全国中小企業団体中央会などの各種調査によれば、中小企業の賞与は大企業ほどの伸びを見せておらず、同じ産業内においても支給額に数十万円の開きがあるケースもあります。
こうした格差は、社員のモチベーションや離職率に影響を与えるだけでなく、業界全体の人材流動性にも影響を及ぼします。一部の企業では、従業員から「より給与や賞与の多い会社へ移りたい」といった声も挙がり、中小企業の人材確保がますます難しくなる懸念もあるのです。
ただし、中小企業の中にも、働き方改革や独自の報酬制度を導入している会社もあり、賞与だけに焦点を当てるのではなく、総合的な福利厚生や働きやすさによって人材を惹きつけているところも増えつつあります。
■ 非正規労働者への恩恵は限定的
今回発表された平均賞与額は、主に正社員を対象としたものです。そのため、パートやアルバイトといった非正規雇用者に対しては、必ずしも同様の還元がなされているわけではありません。
日本では全労働者のおよそ4割を非正規雇用者が占めています。物価上昇や社会保険料の負担増といった生活への影響が広がる中で、一部には「大企業の景気回復が私たちの生活に直結しない」と感じている人も少なくないでしょう。
このような実態がある中で、企業や政策立案者には、賞与や賃金改善の恩恵を幅広い層に届けるための工夫が求められます。具体的には最低賃金の引き上げや、パートタイム労働者への処遇改善などが検討されるべき点として挙げられます。
■ 家計消費の活性化に期待
企業の業績が回復し、従業員への賞与が手厚く支給されることは、消費意欲の向上を促す重要なトリガーとなります。夏のボーナス商戦を前に、百貨店や家電量販店、自動車ディーラーなどでは例年以上の販売促進に力を入れており、個人消費の拡大に対する期待も高まっています。
特に物価が高止まりする今、賞与をもとにした生活の安定化・将来への備えは、大きな意義を持ちます。一方で、消費に充てず、貯蓄や投資として蓄える傾向もみられており、個人によるお金の使い方の多様化が今後も進むことが予想されます。
■ 今後の課題と展望
今回の夏賞与の増加は、日本経済の底力や企業努力の成果の一端を示す結果となりました。一方で、企業間、業種間、そして雇用形態による格差問題も改めて浮き彫りになったかたちです。
すべての労働者にとって公正な報酬が確保される社会を実現するためには、企業側には引き続き従業員への適切な利益還元が求められます。また、政府による所得再分配政策や教育・訓練支援、非正規雇用者の待遇改善といった包括的な施策も重要性を増しています。
今後、冬の賞与や来年の賃金交渉の動きを見ていく中で、今回の夏賞与がどのような長期的影響を与えるのかにも注目が集まります。持続可能な経済成長をめざす上でも、企業活動と働く人々の幸福が両立する社会の形が問われている今、私たち一人ひとりが働く環境について関心を持ち続けることが大切だと言えるでしょう。