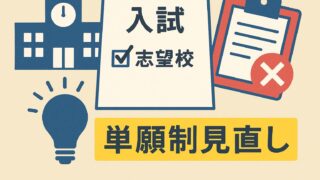「患者の苦しみに正面から向き合う」──医療と命を見つめ続けた女性の静かなる革命
名古屋大学大学院医学系研究科の特任教授であり、緩和ケアの第一線で長年にわたり活躍してきた医師・柏木哲夫(かしわぎ・てつお)さんの姿が大きな注目を集めている。医療の終末期、“死の瞬間”と向き合うという非常に繊細かつ重要な分野で、患者と家族の尊厳に真摯に寄り添ってきた柏木さんは、日本の緩和ケアの黎明期からその発展を牽引してきた人物である。
だが、今回のニュースは彼自身の取り組みではなく、彼の精神を次の世代へと継承し、さらに新たなステージへと引き上げる人物として注目されたのが、医師でありながらドキュメンタリー作家という異色の経歴を持つ安宅(あたか)奈緒子さんだった。
安宅さんは現在、名古屋大学医学部付属病院の特任助教として緩和ケアに携わる一方で、映像や文章を通して医療と人間存在の深い部分に切り込んだ作品を発表している。その中でも、今最も話題を呼んでいるのが、彼女が手がけたNHK「ETV特集」のドキュメンタリー『いのちの対話』である。この番組は、終末期医療に携わる医師や患者、そして家族たちが語る言葉を丁寧にすくい上げ、「死」と「生」の間に宿る静かな希望や痛みを描いたもので、視聴者から多くの反響が寄せられた。
医学者としての訓練と、ジャーナリストとしての感性。これは通常、交わることの少ない二つの道である。しかし安宅さんは、自ら患者と対話を重ね、カメラの前で、またペンの先でその苦しみや希望、涙や笑いを記録することで、「医学の枠」を超えた“人を癒す行為”を実践している。
彼女の原点は、大学在学中に経験したボランティア活動にある。医療支援の現場で見た「言葉にならない痛み」と「現場の限界」。命の現場には、データでは捉えられない“人間の叫び”があることを痛感したという。
卒業後、彼女は国内の大学病院に勤務しながら、多くのがん患者やその家族と向き合う中で一つの核心にたどり着いた。「人は、最期の時間も“生きている”──そこにこそ、わたしたち医療者は耳を傾けなければならない」と。
そして彼女は独学で映像制作を学ぶと、2019年、初となるドキュメンタリー『痛みを聞く』を発表。これは、がん患者たちのケアにおける「声にならない訴え」をテーマにした作品で、医学界のみならずメディア関係者からも高評価を得る。これを機に彼女は“医師であり語り部”という新たな立場を確立し、多くの患者や家族の暮らしの中へと足を踏み入れるようになった。
2024年6月、そんな彼女の活動がYahoo!ニュースで大きく取り上げられた背景には、緩和ケアの現場で今、急速に求められている医師の「変化」がある。つまり、「治すことから支えることへ」、そして「説明することから対話することへ」という流れである。安宅さんのように、言葉や映像を通じて“対話”を続ける緩和ケア医は、まさにその象徴的存在だと言えるだろう。
この記事の核心で紹介された番組「いのちの対話」は、人工呼吸器を外すことをめぐって苦悩する家族、ALS(筋萎縮性側索硬化症)との闘病の中で最後まで意思を表現し続けた患者、意思決定のプロセスに揺れながらも、「その人らしさ」に寄り添おうとする医師たちなど、多くの“いのちのかたち”を丁寧に描いている。
中でも、多くの視聴者が深い感銘を受けたのは、ALS患者の女性が、視線入力を使って「今、生きていることができて、ありがとう」と綴った言葉だった。この言葉に医師である安宅さん自身も心を揺さぶられ、「この瞬間こそが、私が医師として存在する理由だと思った」と語っている。
なぜ、緩和ケアという現場に人はこれほどまでに惹きつけられるのか。それは“死”をタブーとせず、それに真正面から向き合うことで、逆に“生きる意味”を明確に、そして静かに思い出させてくれるからかもしれない。
安宅奈緒子さんのように、同時代の苦しみと希望に寄り添いながら、その真実を自らの価値観で伝える医師の存在は、今後の医療の姿を大きく変える可能性を秘めている。彼女が紡ぐのは、単なる「命の記録」ではなく、「生きた証の証言」なのだ。
現在、安宅さんは大学で学生たちとともに「いのちと医療の対話」の授業を展開している。言葉で救われる患者がいる、声にならない痛みに耳を澄ますことができる医師でありたい──そう語る彼女の姿には、医療の未来が確かに宿っている。
いのちが有限であることは誰もが知っている。しかし、その“限りある時間”をどう生きるのか──その問いに医療がどう応えられるのかを模索するのが、緩和ケアの役割であり、安宅奈緒子さんの挑戦である。やがてその静かな革命は、日本の医療の根幹をも揺り動かしていくことになるだろう。