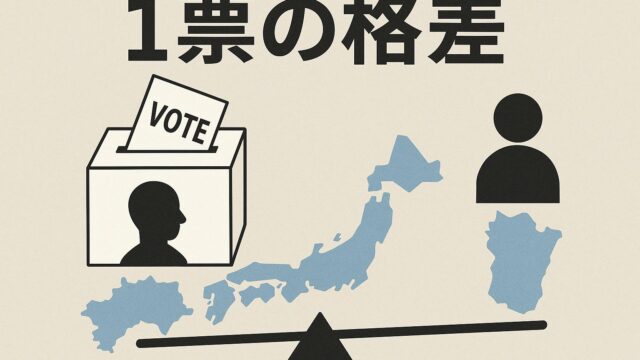近年、我が国を取り巻く安全保障環境は大きく変化しており、海上保安庁の役割はますます重要になっています。領海警備や海難救助、漁業取締り、海洋環境保全など多岐にわたる業務に従事する職員には、高度な知識と技術、そして強い使命感が求められています。
しかしながら、そうした中で海上保安官の離職が近年増加しているという報道がありました。その中でも特に注目を集めているのが「転勤NG」という若手職員のニーズが背景にあるという点です。本記事では、海上保安官の離職増加の背景にある課題や、その根底にある働き方に対する価値観の変化、そして今後の対応策について考察していきます。
海上保安庁における転勤の事情
海上保安庁は、日本全国沿岸に配置されている保安部の間で転勤があります。これは、職務経験を積むため、また全国的なバランスを保つために必要とされてきました。たとえば、初任地が北海道・稚内だった職員が、数年後には沖縄・石垣島へと異動になることもあるのです。また、艦船勤務と陸上業務とを交互に経験する場合もあり、その都度、居住地が変化することになります。
こうした転勤は、組織としての機動力を維持するためには不可欠とされてきました。しかしながら、近年の若手職員の中には、「転勤が多すぎる」「慣れた土地を離れたくない」といった意見も増えており、これが離職の一因となっているとの指摘があります。
価値観の変化と「転勤NG」世代
日本社会全体において、働き方や仕事への価値観は年々変化しています。かつては“転勤は当たり前”という意識が強く、会社員であれば数年ごとの異動も普通のこととされていました。しかし令和の時代、若い世代の多くは「プライベートの充実」や「住み慣れた土地での生活」、「家族や友人との距離感」を重視する傾向があります。
海上保安官も例外ではありません。結婚や育児、介護といったライフイベントを抱える中で、頻繁な転勤が生活に大きな影響を与えることとなっています。とりわけ、共働き夫婦が増加する現在において、一方が全国転勤を伴う職種であることは、家計や子育てへの支障をきたすことがあります。
さらに、海上保安官という仕事は、そもそもが厳しい勤務条件を持ちます。24時間体制の勤務、長期の洋上業務、夜間出動など、身体的・精神的な負荷が大きく、それに加えて頻繁な転勤があるとなると、「続けたい仕事だけれど、家庭との両立が難しい」と感じてしまう若手職員も少なくないのです。
人手不足の中での離職増
海上保安庁が直面する課題の一つは、職員の数が十分ではない中での離職増加です。2023年度には、海保を去る若手職員の数が例年より増加しているという報告もあります。これは、組織の円滑な運用に支障をきたす可能性があり、大きな懸念材料となっています。
今年に入り、全国の地方海上保安部を訪問した石井海上保安庁長官も、現場から「転勤が多くて生活設計が困難」「家族への負担が大きい」という声を直接聞いたといいます。こうした現場の声を受けて、同庁では制度改革に乗り出す方向性も模索されています。
既にパイロットや機関士といった特殊技能を持つ職種では、一定地域での勤務を継続できるよう、転勤を抑える運用が始まっているとのことです。今後は、それ以外の職種にもこうしたフレキシブルな勤務体系を広げることが期待されています。
今後の方向性と課題
海上保安官の離職を抑制し、持続可能な組織運営を実現するためには、従来の組織運用の見直しが不可避です。その中でも、以下のような施策が注目されています。
1. 地域定着型勤務の拡充
長期間、同一地域で勤務可能な制度を整備することで、職員の生活設計に対する不安を軽減する。全国転勤型と選択制を導入するなど、より柔軟な人事制度が求められます。
2. 家族のサポート体制の強化
育児や介護を支援するためのサポート体制(住宅手当、教育支援、配偶者支援など)を拡充することで、家族との両立を後押しします。
3. 働き方の多様性推進
リモートで対応できる業務や、短時間勤務、フレックスタイム制の導入検討など、時代に合った働き方を模索する必要があります。
4. 組織文化の見直し
「我慢して働くのが当たり前」というような固定観念を打破し、職員一人ひとりの声に耳を傾ける組織風土の構築が必要です。
海上保安官は、国民の生命と財産を守る重要な任務を担っています。その強い使命感に支えられて現場に立ち続ける職員が多い一方で、制度面の課題やライフスタイルとの不一致が離職の要因になっているという事実も直視しなければなりません。
結びに――海を守る“人”を守る取り組みへ
最後に、私たち国民一人ひとりに求められるのは、海上保安官という仕事への理解と敬意です。日々、厳しい環境の中で任務に当たる彼ら・彼女らが、安心して働ける環境づくりが急務となっています。そのためには、海上保安庁組織内だけでなく、国全体としての働き方改革の一環として取り組む必要があります。
「転勤NG」という声には単なる我儘ではなく、時代の移り変わりや多様な価値観への対応が求められているというリアルな背景が存在します。この現実を受け止め、柔軟で人に優しい制度を築いていくことこそ、これからの公共機関運営にとって重要な鍵となるでしょう。
未来を担う若手海上保安官たちが、自らの仕事に誇りと希望を持てるような職場環境を整備することで、より強く、信頼される組織への進化が可能になります。それは、私たちの安全な海と社会を守るための、最も本質的な努力でもあるのです。