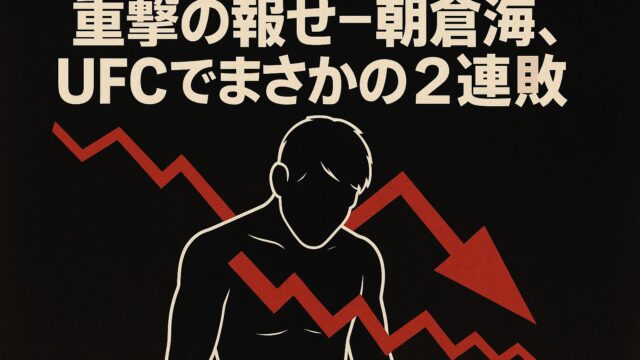体操五輪メダリスト・村上茉愛さん、“性的コメント”に感じた違和感とその思い
東京オリンピックで体操日本代表として銅メダルを獲得した村上茉愛さんが、自身に寄せられる“性的コメント”について、率直な思いを語りました。心の中に蓄積されていた違和感を言葉にしたその姿勢は、多くの人々に深い共感と考えるきっかけを与えています。
アスリートが感じる“視線のズレ”
村上さんは、幼い頃から体操に打ち込み、世界の舞台で日本を代表して戦ってきた一流アスリートです。自己表現の一つとして磨き上げた演技は、技術・芸術両面で高く評価され、2021年の東京五輪ではゆか種目で銅メダルを獲得、女子体操界の歴史に新たな1ページを刻みました。
しかし、アスリートとしてのパフォーマンスとは別に、村上さんが日常的に耳にしてきたのが、彼女の外見や競技中の姿に対する“性的な視線”や“軽い気持ちから放たれるコメント”でした。
SNS時代において、ファンとアスリートが直接つながれる利点がある一方で、その自由なコミュニケーションが、時に一線を越えてしまうことがあります。村上さんが受け取ってきた“セクシー”“エロい”といった言葉は、つい言ってしまった一言かもしれません。しかし、その言葉が本人にとってどれだけ強い違和感やストレスとなっているかは、受け取る側にしか分からないリアルな感覚です。
「スポーツを性的対象として見ないでほしい」
村上さんは、アスリートが筋力や柔軟性、体幹を鍛えて築き上げる身体を「鍛錬の結果」として尊重して欲しいと願っています。しかし「女性だから」「見た目がかわいいから」という理由で外見にばかり注目されることや、筋肉美を性的な視線で語られることには、明確な違和感があったと述べています。
体操という競技は、その演技中に衣装の露出が多くなりがちですが、これは競技の特性に基づくものであって、決して観る側に性的なイメージを持たれるためのものではありません。演技のために必要なデザインであり、それを恣意的な解釈で評価する行為は、アスリートの思いとかけ離れたものです。
村上さんはSNSでの自身の言葉を通して、「選手の気持ちに寄り添ってほしい」「パフォーマンスを正しく見てほしい」と訴えました。その発信は、特定の誰かを批判するものではなく、広く社会に対して「考えるきっかけ」を提供したものでした。
共感が広がる思い——“声をあげてよかった”
このメッセージに対し、「よくぞ言ってくれた」「同じような経験をした」と、多くの共感の声が寄せられたと言います。特に、スポーツ界に限らずメディアや芸能分野でも、似たような経験を持つ人々にとって村上さんの言葉は、自分の気持ちを代弁してくれる存在でした。
アスリートや女性に限らず、人がその能力や働き、努力で評価される社会であるべきというシンプルな価値観のもと、村上さんの一歩は、誰もが安心して輝けるための大事な一歩だったのではないでしょうか。
声を上げることの難しさ
注目度の高い人物が、自分の違和感を言語化するには大きな勇気が必要です。特に、SNSなどで発信する際は、その言葉がどんな形で伝わるか、どんな反響があるかを恐れて躊躇してしまうこともあるでしょう。
それでも村上さんが勇気を持って「こういうコメントが傷つく」と伝えたことは、多くの人にとって、これからの見方、表現、そしてSNS上での発言マナーを見直す契機になったのではないでしょうか。
彼女は「若い世代のアスリートに同じような思いをさせたくない」という気持ちから発信に踏み切ったとも語っています。その背景には、“次の世代への願い”と“環境をより良くしていきたい”というアスリートとしての、そして一人の女性としての誠実な思いが込められています。
スポーツ観戦文化に問われる転換点
私たちがスポーツを楽しむとき、アスリートの競技力やプレーを中心に応援することが、健全なスポーツ文化の基本といえるでしょう。しかしながら、選手のまとうユニフォームに対する過度な注目や性的な言及、見た目ばかりに価値を見出すような視点は、スポーツ本来の価値を損なわせてしまう恐れがあります。
今後のスポーツ観戦や応援文化においては、「アスリートの人間としての尊厳を守る」視点が以前にも増して重要になるはずです。観る側のマナー、聞く側の心情、そして言葉の重さ。それぞれが交差する今の社会だからこそ、より一人ひとりが配慮を持つ必要があるのです。
まとめ——一人の言葉が社会の意識を変える
村上茉愛さんの勇気ある発信は、単なる“つぶやき”ではなく、社会に必要なメッセージでした。誰かを批判せず、ただ感じた思いを正直に表現することで、同じように悩んでいる人々の背中を押し、少し先の未来を明るく照らすことができる。そんな力を、彼女の言葉は持っていたのです。
これを機に、私たち一人ひとりがSNSでの発言はもちろん、日常のふとした言動においても、「その言葉の先に誰がいるか」を考えることができれば、今よりもっと優しく、思いやりに満ちた社会に近づけるのかもしれません。
表現の自由が尊重される社会だからこそ、その自由を使う私たちの側にも責任があります。そして、アスリートたちがその能力と努力で純粋に輝ける未来を、社会全体で支えていきたい——そう願わずにはいられません。