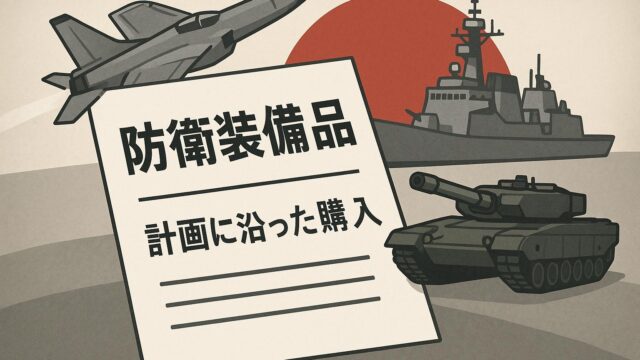「実家暮らしでも自立」──この言葉に、あなたはどういったイメージを持つでしょうか。実家に住み続けることに対して、「甘えている」「自立できていない」といった偏見や否定的な印象を持つ方も少なくないかもしれません。しかし、実際には住まいの形と精神的・経済的な自立とは必ずしも一致しないということに、最近ようやく社会も気づきはじめています。
2024年6月、共同通信社が配信したYahoo!ニュースの記事「実家暮らしでも自立 当事者らの声」は、こうしたテーマを取り上げ、当事者の声を通して新たな視点を私たちに提供しています。本記事では、その内容を紹介しつつ、現代社会における「自立」と「実家暮らし」の関係について考えていきます。
変化する「自立」の概念
かつては、実家を出ることが「大人として自立する第一歩」とされていました。大学進学や就職を機に一人暮らしを始める若者が多く、それが社会的にも「普通」とみなされる風潮がありました。特に都市部では、それが一種のステータスとして語られることもありました。
しかし、生活費の上昇、給与水準の伸び悩み、不安定な雇用環境──こうした現実が、若年層にとって自立の定義を見直すきっかけになっているのです。
記事では、障害を持ちながら実家で暮らす20代の女性が登場します。彼女は大学を卒業し、現在はフルタイムで働き、家計に対しても貢献しているとのこと。家事もこなしており、「自分なりに自立している」と強調します。その言葉には、依存ではなく、合理的な選択として「実家」という選択肢を採ったことへの自信が感じられます。
また、家族との共同生活は精神的な支えともなり、特に心身の状態に不安がある人にとっては大きな安心材料でもあります。経済的な自立だけではなく、精神的な余裕もまた「自立」に欠かせない要素であると考えれば、実家で暮らすことは合理的かつ有効な方法と言えるでしょう。
当事者の声に耳を傾けて
この記事が意義深いのは、当事者の声が直接紹介されていることです。実家で暮らしている人たちは、それぞれに理由があり、事情があります。単に生活が楽だからという安易なものではなく、障害、経済状況、家庭環境、地域の住宅事情など、多様な背景があるのです。
また、ある40代の男性は、学生時代からそのまま実家に住み続け、現在は両親の介護をしながら仕事をしているとのこと。彼にとって実家暮らしは親との共生だけでなく、家族の一員としての役割を果たすための選択です。こういった事例は、実家にいることが「甘え」ではなく「責任ある決断」である場合も多いことを示しています。
「精神的にも経済的にも自立しているかどうか」に目を向ければ、住む場所の選択は相対的なものであるべきです。一人暮らしだからといって必ずしも完全に自立しているとも限らず、実家暮らしであっても立派に生活を営んでいる人は少なくありません。
若者支援の現場から見た「実家暮らし」
支援活動を行うNPOなどでは、若者の自立支援の一環として「実家暮らし」を肯定する風潮も広がっています。経済的余裕がない中で無理に一人暮らしを選ばせることは、むしろ若者を追い詰める結果になりかねないからです。
特に、所得が不安定な非正規雇用者や働きながら資格取得を目指す人たちにとって、実家に住むことで生活を安定させ、次のステップへと進む土台を築くことができます。こうしたケースを「移行期の戦略」として捉えることで、柔軟な支援が可能になります。
また、家族で協力して生活する中で、料理や掃除、親のサポートを日常的に行う人もいます。これらは一人暮らしの中で身に付けるスキルと何ら変わらず、「生活力」そのものと言えます。
社会の認識アップデートを
この記事が私たちに訴えかけているのは、固定観念から解き放たれた多様な「自立」の形に対する寛容さと理解です。時代が変わる中で、ライフスタイルや家族の在り方も変わっていきます。それに伴って、「自立」もまた一つの答えではなく、いくつもの選択肢を持つ柔軟な概念として捉えられるべきです。
一人暮らしをしているから偉い、実家暮らしだから甘えている──こんな単純な価値観では、多くの現代人のリアルな暮らしを理解することはできません。
情報過多の時代だからこそ、私たちはあらゆる立場の声に耳を傾け、偏見に基づかない判断力を養う必要があります。そして、誰かの生き方を簡単に評価するのではなく、その背景と意志を尊重することで、より多様で包摂的な社会が実現するのではないでしょうか。
さいごに
「自立とは何か?」という問いには、明確な答えはありません。それぞれが自分らしく生きるために選んだ形が、その人にとっての自立なのです。
大切なのは、その人が生きたいとするスタイルを実現できているかどうか。そして困った時に助けを求められる環境と支援が存在するかどうか。実家にいても、家族と協力して生活することで得られる安心感や、本当に必要なサポートの手を差し伸べ合える関係性もまた、自立への重要な一歩だと言えるでしょう。
今一度、実家暮らしに対するステレオタイプを見直し、もっと温かく、理解のある目で捉えていきたいものです。私たち一人ひとりが「多様な自立」のあり方に寛容になれば、より生きやすい社会が少しずつ形作られていくことでしょう。