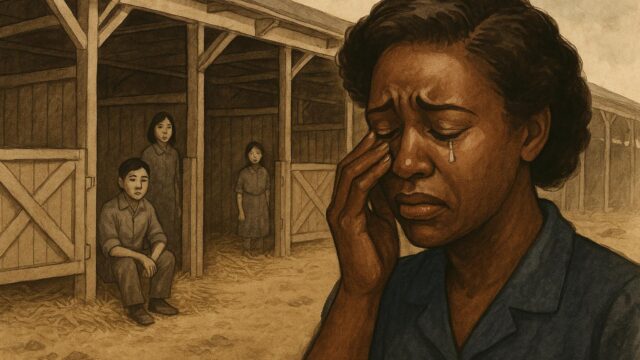最近、全国的に水ぼうそう(正式名称:水痘)が大流行しており、特に子どもを中心に罹患者数が増加しています。水ぼうそうと聞くと、比較的軽い子どもの病気というイメージを抱く方も多いかもしれませんが、実は大人が罹ると重症化するリスクも高く、注意が必要な感染症です。今回は、水ぼうそうの症状や感染経路、予防方法、そして大人が注意すべきポイントについて詳しく解説します。
水ぼうそうとはどんな病気?
水ぼうそうは「水痘・帯状疱疹ウイルス(VZV)」によって引き起こされるウイルス感染症です。感染すると、赤く小さな発疹が身体中に現れ、やがてかゆみを伴う水疱(みずぶくれ)となります。一般的には軽度の発熱を伴い、約1週間ほどで症状は落ち着いてきます。しかし感染力が非常に強く、空気感染、飛沫感染、接触感染を通して周囲の人にも広がります。
水ぼうそうは一度かかると多くの場合は免疫ができ、二度とかからないと言われていますが、ウイルスは体内に潜伏し続け、後年「帯状疱疹」として再発するケースがあることも知られています。
なぜ今、水ぼうそうが流行しているのか?
今回の水ぼうそうの流行は、コロナ禍を経て感染症対策(マスクや手洗い、対人距離の確保など)が徹底されていた期間中に、多くの子どもたちが水ぼうそうに感染する機会を持たなかったことが一因と考えられています。その結果、集団での免疫が薄まっており、接触機会が増えた今、感染が広がりやすくなっているのです。
厚生労働省の発表によると、2024年の初夏頃から乳幼児を中心に水ぼうそうの報告数が急増しており、例年と比べても高い水準で推移しています。特に保育施設や幼稚園、小学校低学年など、子ども同士の接触が多い場での感染が目立ちます。
水ぼうそうの主な症状と経過
感染してから約2週間の潜伏期間の後、発熱とともに赤い発疹が全身に現れ始めます。発疹は時間とともに水疱へと変化し、次第にかさぶたとなって治っていきます。発熱や全身倦怠感、頭痛、かゆみなどを伴うため、非常に不快な状態が数日から1週間ほど続きます。
通常は軽症で済むことが多いですが、免疫力が低下している人や基礎疾患を持つ方は重症化することがあります。また、発疹の痕が化膿すると跡が長期間残る可能性があります。
大人の水ぼうそうは要注意
子どもの頃に水ぼうそうにかからなかった大人は、感染した際の症状が子どもと比べて遥かに重い傾向があります。高熱や激しい頭痛、倦怠感に加えて、水疱が広い範囲に及び痛みやかゆみが強く出ることが一般的です。
さらに、大人の水ぼうそうでは肺炎、脳炎、肝炎などの合併症を伴うケースも報告されており、入院が必要となることも少なくありません。特に妊婦が感染した場合、お腹の赤ちゃんに影響を及ぼすリスクもあるため、注意が必要です。
また、大人は「水ぼうそうにかかるはずがない」と思い込み、初期症状を見逃しやすい点にも注意が必要です。普段と違う発熱や皮膚症状が見られた際には、すぐに医療機関で診察を受けることが大切です。
感染を予防するには?
水ぼうそうには有効なワクチンが存在します。日本では2014年から水ぼうそうワクチンが定期接種となり、1歳と3歳で2回接種することが推奨されています。しかし、大人で一度も感染したことがない、または予防接種を受けたか記憶にないという方も多く、必要に応じて任意接種を受けることも検討できます。
特に、以下のような方は予防接種の検討が推奨されます:
– 子どもと接する機会が多い大人(保育士・教員・医療従事者など)
– 妊娠を希望している女性
– 海外旅行の予定がある方(海外では水ぼうそうが重症化しやすい地域もあります)
また、基本的な感染症対策として、手洗いやうがい、人混みに出る際のマスク着用などを続けることは、水ぼうそうのみならず様々な感染症の予防につながります。
感染が疑われる場合の注意点
水ぼうそうは感染力が非常に強いため、感染が疑われる症状が出た際には、すぐに学校や勤務先を休み、他人との接触を避けることが大切です。医療機関を受診する際には、事前に連絡を入れてから受診するようにしましょう。院内感染を防ぐための措置として、別室での待機や別ルートでの診察などが行われることもあります。
特に、家庭内に乳児や高齢者、疾患を持つ方がいる場合、感染が拡大しないようにするためにも、迅速な対応が求められます。
子どもたちの健康を守るために大人ができること
今回の流行を受けて、私たち大人ができることは何でしょうか。まずは、子どもたちが予防接種をきちんと受けているか確認し、もし未接種であれば医療機関と相談して早めに接種することが重要です。
また、自身の感染歴や予防接種歴についても改めて確認し、必要に応じて抗体検査やワクチン接種を行うことが望まれます。家族や友人に小さなお子さんがいる場合には、無症状でもウイルスを拡げてしまう可能性があることから、自分自身の体調管理を徹底することが求められます。
まとめ:水ぼうそうは「子どもの病気」と油断しないで
水ぼうそうは一見、子どもがかかる軽い病気だと思われがちですが、実際には感染力が高く、大人がかかった際には重症化するリスクもある、決して油断できない感染症です。
現在の流行を受け、子どもも大人も広く注意が必要です。予防接種の確認と接種、基本的な衛生管理、そして早期の受診と適切な対応によって、感染拡大を防ぐことが可能になります。私たち一人ひとりが正しい知識を持ち、行動を改善することで、周囲の大切な人を守ることができます。
特に家族に乳幼児や高齢者がいる方は、自分自身の健康管理が周囲の人々の安全にも直結することを忘れず、今後の行動に生かしていきたいものです。