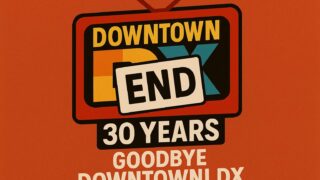政界において再び注目を浴びる人物がいます。元農林水産副大臣である吉川貴盛(よしかわ・たかもり)氏。7月に公職選挙法違反(被買収)罪に問われた裁判の判決が控える中、本件が大きなメディア露出とともに再燃しています。かつて北海道を代表する自民党の実力者として知られた吉川氏の歩みと、近年の動きから政治倫理の根幹が改めて問われています。
吉川貴盛氏は1950年2月20日、北海道砂川市に生まれました。北海道大学を卒業後、北海道庁に入庁。地方行政に携わる中で政治の道を志し、1996年に衆議院に初当選。以来、2020年の辞職まで通算8回当選し、農林水産行政を中心に政策分野で存在感を発揮してきました。
2006年の第一次安倍内閣では内閣府副大臣に就任し、環境、観光政策など広範な分野に関わりました。特に農政に関しては地元北海道の農業関係者と深いつながりを持ち、第一次安倍内閣以降、農水政策の中核を担う人物として幾度も農林水産関係の役職を歴任。2018年には農林水産大臣に就任し、農業の輸出強化やスマート農業の推進に力を入れました。
しかし、そんな輝かしい実績の影で2020年、任期中の不祥事が報じられることになります。吉川氏は鶏卵生産大手「アキタフーズ」の元代表から現金500万円を受け取ったとして、東京地検特捜部から捜査を受けることとなりました。2020年末には健康上の理由を挙げて国会議員を辞職。本人は一貫して“現金は受け取ったが賄賂ではなく、政治献金の一部や相談料のようなものだった”と主張し、裁判で争ってきました。
今回注目されたのは、その賄賂とされた現金が実際に「何の見返りもなかった」という趣旨の主張が審理で展開され、証人として出廷した関係者も「働きかけがあったとは認識していない」と証言したという内容です。かつて国政の中枢で活躍した政治家の潔白か有罪か。その分水嶺を全国が見つめています。
政治家と企業の金銭授受に関する問題は、吉川氏のケースに限らず、何十年にわたって日本の政治に横たわってきた問題です。田中角栄元首相のロッキード事件、竹下登政権下のリクルート事件など、政治とカネを巡る疑惑は時代を越えて繰り返されてきました。
吉川氏の裁判では、収賄の意図があったかどうか、職務権限との関連性が厳しく問われています。ちなみに公職選挙法違反の被買収とは、権力者に対して金銭を渡して「見返り」を期待していた場合に成立するもので、賄賂でないという主張が通るか否かは、職務との結びつき、そして金銭の性格に大きく左右されます。
検察側は、アキタフーズ側が政治の場で業界利益を推進してもらう意図をもって現金を渡したと主張。一方、弁護側は吉川氏が賄賂としての認識を持っていなかったとし、「鶏卵業界の取りまとめ役として信頼されていただけだ」と反論。結果として、鶏卵業界に有利な政策が打ち出されたかどうかも重要な争点とされています。
この裁判が注目される一因は、単に一人の政治家の有罪・無罪だけでなく、政治家と業界団体、企業との距離感、特に地方政治家と地元産業との関係に対する国民の見方が問われているからです。北海道のように農業、畜産業が地域経済の根幹をなしている場合、政治家と業界の繋がりは切っても切れません。その中で、どこまでが適切な関係で、どこからが越えてはならない一線なのか、本裁判の判決は今後の政治活動に与える影響は小さくないでしょう。
吉川氏の弁明や主張には、「長年の政治活動で養ってきた信念」や「地元の期待を背負って働いてきたという自負」が垣間見えます。一方で、社会全体が政治家に求めるクリーンさも年々増しています。「政治とカネ」の距離を測るものさしは、過去の基準とは異なり、「疑わしきは罰す」の風潮すら孕んでいます。
7月に予定される判決を前に、吉川氏が残してきた議会活動や政策実績が再評価されると同時に、疑惑の真偽が公に裁かれる場となるこの裁判から、私たちが学ぶべきことは少なくありません。政治における倫理とは何か、信頼を築くとはどういうことか。市民一人ひとりが政治との距離を考える契機となることでしょう。
かつて、「農政の吉川」とも呼ばれ、北海道の農業政策推進の象徴だった吉川貴盛氏。その歩みは、政治の現場が抱える複雑な利害関係と、公正さのジレンマを私たちに映し出しているのかもしれません。