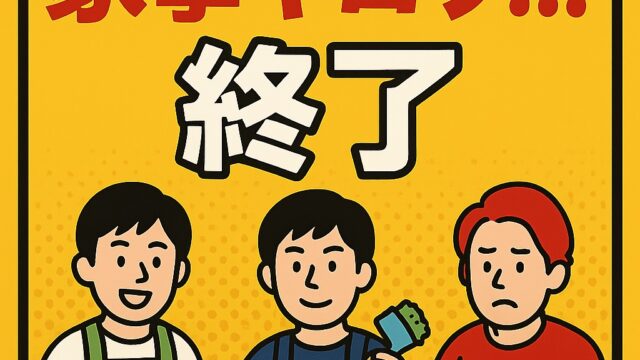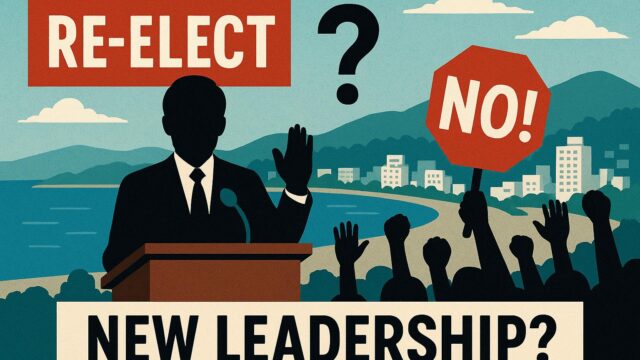「保育園の洗礼」職場の理解は:子育てと仕事の両立に必要な社会のまなざし
子どもを保育園に預け始めると、想像以上の大変さに直面する親は少なくありません。特に初めての保育園通いとなると、慣らし保育のスケジュール、頻繁な体調不良、そして急な呼び出し。いわゆる「保育園の洗礼」と呼ばれる試練が、働く親たちを待ち受けています。そしてその試練を乗り越えるために大きなカギとなるのが、職場の理解と協力体制です。
この記事では、子育てと仕事を両立する上で直面する課題、そしてそれに対する周囲の理解や仕組みづくりの重要性について、多くの共働き家庭の実情をもとに考えていきます。
「慣らし保育」は想像以上に大変だった
保育園への入園が決まっても、すぐにフルタイムで預けられるわけではありません。多くの園では「慣らし保育」といって、少しずつ保育時間を長くしていくステップを取り入れています。最初のうちは2時間、次の日は半日、1週間後にようやく1日。その間、親は仕事を調整しなければならず、在宅勤務で乗り切るケースもあれば、有給を使い切ってしまう人もいます。
あるお母さんは、復帰前に十分な準備をしていたつもりでも、「こんなに休まなければならないとは思わなかった」と振り返ります。保育園に預け始めたばかりの子どもは環境の変化に敏感で、自宅と保育園を行き来する中で体調を崩しやすいもの。しかも同じタイミングで同じような症状が園内で流行し、家でも対応に追われることになります。
仕事に復帰しても、「急な呼び出し」が待っている
仕事に復帰してからも、安心はできません。熱が出た、おう吐した、下痢をした——保育園からの呼び出しは、親の勤務時間中に突然やってきます。急いでお迎えに行き、場合によっては数日間の自宅療養。特に入園から最初の1年間は「月の半分は病欠」というケースも珍しくありません。
これによって、親の仕事にも大きな影響が出ることがあります。急な早退や欠勤で、チームに迷惑をかけるのではとプレッシャーを感じたり、働く自信を失いかけたりすることも。復職したばかりの頃は業務への慣れも必要で、なおさら心身ともに消耗する時期です。
それでも子どもにとっても親にとっても、大切な「社会との第一歩」
こうした大変さの中にあっても、保育園は子どもにとって初めての「社会との接点」です。先生やお友達と関わる中で、生活リズムや集団行動を身につける大切な場であり、親にとっても育児を「1人で抱えない」という最初の一歩と言えます。
「朝、泣きながらバイバイしていた子が、数ヶ月後には笑顔で登園するようになった」「はじめて“せんせい”という言葉を覚えて得意そうに話してくれた」——親たちの体験談には、保育園生活を通じて日々成長していく子どもの姿、それを見守る幸せな時間が詰まっています。その原動力があるからこそ、苦労してもがんばれる。きっと多くの親が共感できる気持ちではないでしょうか。
社会や職場の「理解」と「支援」が不可欠
とはいえ、こうした育児と並走する勤務状況に耐えられるかどうかは、職場の環境や上司・同僚の理解に大きく左右されます。急な休みにも寛容でいられる仕組みづくり、同じ立場の社員同士で支え合える風土、フレックスやリモートワークの柔軟性——これらが整っていれば、一人で全部背負わずにすみます。
政府や自治体でも「イクボス」推進や育児支援の働きかけが行われていますが、実際には「制度はあるけど使いづらい」という声も根強いのが現状です。人手不足の現場では「休まれると困る」という本音もあるでしょう。でも、誰もが子ども時代を経て社会で育まれてきたことを思えば、「次世代の育成」は決して誰か一部の人の問題ではありません。
「保育園の洗礼」にも、みんなで乗り越えられる社会へ
今、子育て世代の親たちは、「働くこと」と「育てること」の両立を真剣に考え、暮らしの中で様々なトライ&エラーを繰り返しています。保育園に入ること、仕事に復帰することはゴールではなく、また新しいステージのスタート。
大変さの中にも、子どもの笑顔や成長を通して得られる喜びがあり、そんな日々をそっと支えてくれる職場や周囲の理解があれば、どんなに心強いことでしょう。「小さい子どもがいる親は大変」というだけでなく、「世代を越えて誰もが支え合える社会」を目指して、いま必要な変化に目を向け、協力の手を差し伸べることが、これからの日本社会にとって欠かせない視点です。
どの家庭にも、子育てのストーリーがあり、それぞれの「保育園の洗礼」を経験しながら、親子は少しずつ日々を乗り越えています。その歩みに、もっと優しく寛容な社会の目が向けられることを願ってやみません。