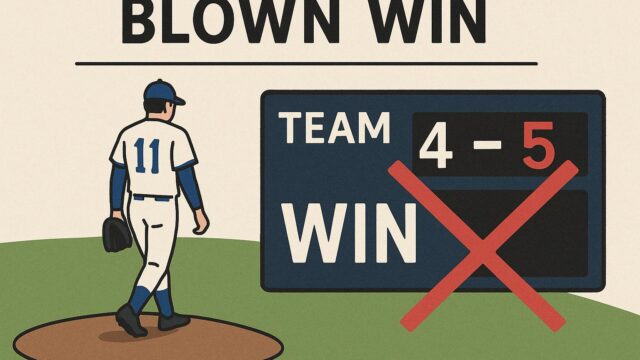【産後うつの現実──一人で抱え込まないで】
2024年6月、神戸市北区で起きた痛ましい事件が報道されました。産後まもない母親が生後7か月の長男を殺害した疑いで逮捕され、「精神的に不安定だった」との供述をしていたことが発表されています。この事件は、多くの家庭が経験する「出産」という新たな生命の誕生に隠された影の部分──「産後うつ」の問題を改めて社会に投げかけるものとなりました。
この記事では、報道された事件を起点として、産後うつの現状、その背景、必要な支援体制について掘り下げていきたいと思います。誰もが安心して子育てできる社会を目指すうえで、産後うつとその支援について考えることは必要不可欠です。
■ 事件の概要と母親の背景
報道によると、逮捕された母親は30代。2023年11月に長男を出産し、2024年6月にその命を奪った疑いで逮捕されました。母親は「子どもを死なせた」と自身で119番通報し、警察に逮捕されるに至ったとのことです。取り調べに対して「出産後から精神的に不安定だった」と話しており、調査の結果、出産以降の状況や家庭環境、精神状態に焦点が当てられています。
警察は今後、事件の背景にある産後うつや精神的な影響について、専門家の診断も含めて慎重に調べていく見込みとのことです。
■ 産後うつとは?
産後うつは、出産を経験した女性のうち10~20%程度が経験するとされる精神的な不調です。産後2週間から数か月以内に発症することが多く、主な症状として、気分の落ち込み、不安感、涙もろさ、集中力の低下、食欲不振、睡眠障害、自責の念、育児放棄の傾向、死にたいと思う気持ちなどが挙げられます。
これは決して「気の持ちよう」や「母性の欠如」ではありません。ホルモンバランスの急激な変化、育児による睡眠不足、環境の変化、サポート不足、孤独感など複数の要因が複雑に絡み合って発症する「医学的な状態」です。
特に日本では「母親なんだから頑張らなければ」「赤ちゃんのために」と自分を追い詰めてしまい、つらさを口に出せず一人で抱え込む人が少なくありません。
■ なぜ誰にも頼れない?
今回の事件でも注目されているのは、母親が「孤立していた可能性が高い」という点です。多くの母親は赤ちゃんと1対1で過ごす中で、会話の機会が減り、生活リズムも変わり、社会とのつながりが薄くなりがちです。それに加えて、「母親失格だと思われたくない」「弱音を吐いちゃいけない」というプレッシャーから、親族やパートナー、行政や医療機関などに助けを求められないという負のスパイラルに陥ってしまいます。
特に、核家族化が進んだ現代において、親や兄弟も遠方に住み、近くに頼れる人がいないという環境では、育児の孤独感はさらに増していきます。
また、パートナーや家族の理解不足が、母親の不調を見逃してしまうという例も少なくありません。「家にいるんだから楽だろう」といった無理解な言葉が、産後の母親をより追い詰めてしまうこともあります。
■ 支援体制は十分なのか?
日本では、ここ数年でようやく産後ケアへの取り組みが進み始めています。一部自治体では助産師や保健師による訪問ケア、相談窓口、産後ケア施設の案内などが整備されています。しかし、そうしたサービスを「自ら」利用するには、情報収集力や行動力が必要であり、すでに精神的に不安定な状態にある母親にとって、それは簡単なことではありません。
また、自治体ごとに支援の内容や範囲が異なっており、地域差も大きな課題です。産後うつの母親にとって「支援がある」という情報自体が届いていない場合も多くあります。
さらに、育児のパートナーである父親や周囲の家族への啓発も必須です。母親の異変にいち早く気付くためにも、周囲が「産後うつとは何か」を十分に理解し、気づいた時点ですぐに医療機関や支援窓口に繋げるチャンスを逃さないことが求められます。
■ 産後うつを防ぐために私たちができること
私たち一人ひとりができることは何でしょうか?
それは、まず「産後うつは誰にでも起こりうるもの」という正しい認識を持つことです。母親の頑張りや愛情の深さに関係なく、産後うつは突然やってきます。そして、それは決して恥ずかしいことでも、我慢すれば治るものでもありません。
家族、友人、同僚、近所の人など、母親を取り巻く私たちが「最近、元気がないな」「様子が違うな」と感じたら、さりげなく声をかけたり、話を聞く時間を作ったりするだけでも、母親は「ひとりじゃない」と感じられるかもしれません。
また、「眠れてる?」「食べられてる?」「息抜きしてる?」といった具体的な質問を投げかけることで、母親自身が自分の状態に気づくきっかけにもなります。
■ 社会として取り組むべき課題
今回の事件は、誰もが想像しがたいほどの苦悩を抱えていたであろう母親の背景に、多くの課題が潜んでいることを示しています。悲劇を繰り返さないためにも、社会全体で次のような取り組みが必要です。
① 産後うつに関する教育・啓発を強化する
学校教育や企業の研修などで、「出産と育児」に伴う精神的影響について学ぶ機会を増やすべきです。社会人として、親になる前からこうした知識を持つことが当たり前になる社会が望まれます。
② 母親だけでなく父親や家族への支援
育児は母親だけの責任ではありません。父親やパートナーも積極的に家事・育児に関わり、母親の心のケアに寄り添うための支援を制度的にも整える必要があります。
③ 誰もが利用しやすい産後ケアサービスの拡充
心理的・経済的にも利用しやすい産後ケア制度を全国に広げ、母親が「自分のために助けを求めること」に罪悪感を持たない仕組み作りが求められます。
■ 最後に
母親が子どもの命を奪ってしまうという事件は、あまりにも心が痛みます。しかし、それはごく限られた例外として片付けてはならず、「この背景には何があったのか?」「私たち社会は何ができただろうか?」という問いを私たち一人ひとりが親身に考える必要があります。
新しい生命の誕生が、必ずしも「幸せなスタート」ばかりではないという現実を多くの人に知っていただきたい。そして、手を差し伸べる社会、寄り添い合える環境を築くために、今、私たちができることを模索していくことが大切ではないでしょうか。
「育児はひとりで抱え込むものではない。」
この言葉が、すべての母親の心に届く社会の実現を心から願いながら、今回の事件を決して風化させないよう、私たち一人ひとりが立ち止まって考えてみたいと思います。