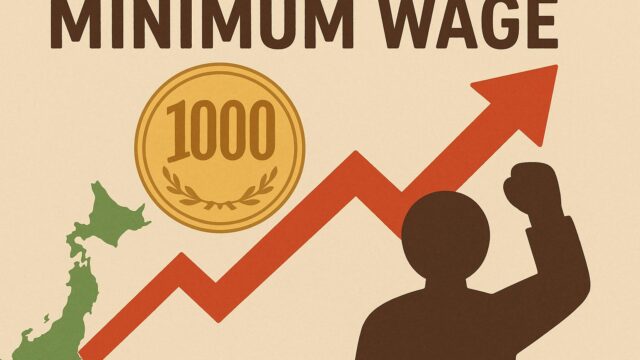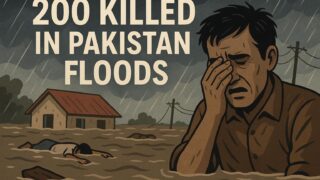「足手まとい」という言葉が引き起こしたもの
記事タイトルにある「足手まといと子殺し」という言葉は、読む者の胸を強く締め付けます。満州からの逃避行で、幼い子どもを抱える母たちが追い詰められ、取り返しのつかない選択に至った事例は、記録や証言に散見されます。そこには、誰かの悪意だけでは説明できない極限状況と、避難の列が生む集団心理、そして「足手まとい」という一言が人の心を蝕む力がありました。
いまを生きる私たちが、その言葉に向き合うことは、過去を糾弾するためではありません。極限の中で人が人であり続けることの難しさを知り、似た構造を現代から取り除くための手がかりを得るためです。
逃避行の現実——「選ばされる」苦悩
満州の開拓地からの撤退は、飢え、寒さ、暴力の恐怖、情報の遮断が折り重なる過酷な体験でした。道も交通も崩れ、乳飲み子の泣き声ひとつが周囲の不安を増幅し、列の視線はときに母子を「危険要因」へと短絡的に位置づけます。「この子がいなければ速く歩ける」「皆の命が助かるかもしれない」——そんな声が、外側から、そして内側の自責の声として母を締め上げる。ここで起きたのは、正義や非情の単純な対立ではありません。体力、食糧、移動速度という物理的制約、守るべき順序を決めざるを得ない集団の圧力、そして親であるがゆえに抱える最大の責任が、同時に母を追い詰めたのです。
だからこそ、私たちは安易に「当時の彼女たち」を裁くことはできません。安全と十分な食事、暖かい部屋から発する正論は、極限の地平で意味を失います。重要なのは、判断の質ではなく、判断を強いてしまう環境そのものを見極めることです。
言葉の暴力性——レッテルが人を孤立させる
「足手まとい」という言葉は、人を能力だけで測る尺度を日常化させます。弱さを抱える人を排除し、沈黙へ追い込む。避難や災害の現場において、この言葉は特に破壊的です。耳にした人は、自らを「迷惑」とみなし、助けを求める権利を手放してしまうからです。私たちにできる最初の対策は、こうした言葉を使わず、使わせず、見過ごさないこと。言葉の風景を整えることは、いのちの風景を整えることと直結します。
証言を聴く姿勢——センセーショナルでなく、丹念に
- 用語への配慮:当事者が選んだ言葉を尊重し、断定的・刺激的な表現で上書きしない。
- 一人称の回復:誰かに語らされた物語ではなく、本人の時間軸と沈黙を含んだ「揺れる語り」を待つ。
- 反証の併読:一つの証言で歴史を塗り替えず、複数資料を並べて構造を捉える。
- 目的の明確化:消費でなく、継承と学びのために読む・聴く。
記憶は事実と感情の複合体です。数字で測ることが難しい領域だからこそ、丁寧さと検証可能性を両立させる工夫が欠かせません。
いまへの宿題——「弱さが置いていかれない社会」をつくる
- 避難計画に「子ども基準」を組み込む:運搬手段、授乳・おむつの動線、静穏スペースの確保。
- ケアの分担:親だけに背負わせず、地域での抱っこ・見守りの仕組み化。
- 言葉の見直し:「足手まとい」を排し、「支え合い」「役割の交代」という語彙を広める。
- 心のケア:極限状況は誰の判断も歪めうるという前提で、事後の心理的支援を標準装備に。
過去の悲劇は、単なる悼みでは終わりません。私たちが具体策に落とし込むとき、初めてその苦しみが次の世代の安全へと姿を変えます。
学びを深めるために
満州からの引揚げや母と子の体験を丁寧に知るには、一次証言や通史の併読が有効です。例えば、藤原てい『流れる星は生きている』は、母の視点から逃避行を綴った名著として知られています。また、半藤一利『昭和史』は、社会の大きな流れの中で引揚げを位置づけ直す助けになります。いずれも多くの版が流通しており、解説や関連資料も豊富です。
さいごに
「足手まとい」という短い言葉が、どれほど深い影を落とすのか。過去の悲劇は、その問いを静かに突きつけています。弱さが抱えられる社会を選び取ること——それが、私たちが受け取るべき最も確かなバトンです。