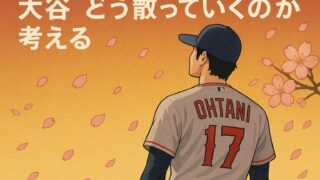大家族の父として一世を風靡した「ビッグダディ」こと林下清志さんが、「多産DV」という近年注目されている社会問題について語った内容が話題を集めています。このテーマは、単なる個人の家族論ではなく、昨今の日本社会に横たわる「家族」「パートナーシップ」「性別役割」などに深く関わる重要な問題でもあります。
「多産DV」という言葉をご存知でしょうか?
一般に「DV(ドメスティック・バイオレンス)」と聞くと、殴る・蹴るといった身体的な暴力や、言葉での攻撃、経済的な制約を強いるといった精神的なものを想像するかもしれません。「多産DV」はこれらに加えて、女性に対して繰り返し妊娠・出産を強要するような関係にあることを指します。つまり、配偶者やパートナーから妊娠を迫られ続けることで、相手に逆らえず、身体的にも精神的にも苦しみを抱えるケースです。
ビッグダディこと林下清志さんは、自身の人生を語る中でこの「多産DV」について触れ、自らの家族観や結婚観を振り返りました。数多くの結婚を経験し、合計で子どもは10人以上といういわゆる「大家族の父」として知られている彼ですが、今回の発言は単なる過去の自己弁護ではなく、複雑な家庭環境の中で見えてきた家族のあり方を、現代社会に問いかけるものでした。
林下さんは、「自分の希望でたくさん子どもが欲しかったのは確かだが、それは自分ひとりの意志ではなく、相手も納得していたものだと思っていた」と語ります。しかし一方で、「本当に相手は心から納得していたのか、声を上げることができなかっただけなのか」という疑問を持ち始めていることを明かしました。
この発言は、多くの人にとって重要な気づきを与えてくれます。
私たちは、パートナーシップの中で「同意」という言葉を口にすることがあります。しかし、「表面的な同意」と「真の同意」は必ずしも一致していません。特に家族や恋愛といった親密な関係において、相手に逆らえなかったり、従わざるを得ないという心理状態での「同意」には注意が必要です。
林下さんが指摘するように、愛情からの決断だったとしても、それが長期的に相手に重荷をかけていたとしたら、それは無自覚のうちに加害性を持ち得るということです。これは家族の中だけではなく、社会全体が考え直していくべきテーマです。
「子どもは多いほど良い」「家族は支え合うもの」——これは一見、美しい理想に聞こえます。しかしそれが、誰か一人に重い負担を背負わせて成り立っているものであるならば、私たちはもう一度立ち止まって考える必要があります。
林下さんはこうも語っています。「自分は子どもが大好きで、家族というものに夢を抱いていた。でも『家族の幸せ』と『相手の犠牲』が釣り合っていなかったのかもしれない」と。その言葉は、彼自身の人生経験からにじみ出た深い反省と見直しの表れであり、私たち一人ひとりにも大切な示唆を与えてくれます。
家庭における「選択」とは、一人だけで完結するものではありません。妊娠や出産は特に、女性に大きな身体的・精神的負担をもたらします。そして男性にとっても、その家庭を維持するための責任や関わり方が問われるものです。だからこそ、夫婦やパートナーとして「本当に納得しているか」「無理をしていないか」など、継続的に丁寧なコミュニケーションを取ることが欠かせません。
ビッグダディの今回の発言は、彼の家庭観やこれまでの行動を棚に上げて語るものではなく、自身の過去と真剣に向き合いながら、社会に向けて発信したメッセージとも言えるでしょう。私たちはそこから何を学ぶべきか。それは、パートナーとの関係性を深く見つめ直し、相手を思いやる姿勢を持つことの大切さではないでしょうか。
また、「多産DV」に限らず、家庭内の問題は非常にデリケートで表面化しにくいものです。女性が「我慢するのが当たり前」と考え、声を上げることに戸惑いを覚えてしまうこともあります。だからこそ、周囲の理解とサポート、そして社会的な意識の変化が必要です。
子どもが多い、家族が大きいということは素晴らしい側面もあります。一方でその舞台裏には、多くの労力・悩み・葛藤が存在し、特に母親にかかる負担は想像を超えるものかもしれません。林下さんのように、育児を積極的に行う男性がさらに増える社会、そして家庭内での意思決定に男女の対等性がしっかりと根付く社会を目指すことが、これからの日本に求められています。
「一人ひとりの意思が尊重される家庭とは何か?」
この問いに対する明確な答えはすぐには見つからないかもしれません。しかし、こうした個人の声に耳を傾け、対話を重ねていくことが、少しずつでも健全な家庭関係、そしてよりよい社会の実現につながっていくのではないでしょうか。
林下清志さんの言葉をきっかけに、私たちも今、自分と向き合い、家族やパートナー、友人など大切な人との関係をもう一度見つめ直す時間を持ってみることが大切だと感じます。「幸せな家庭」を築くために、そこに関わるすべての人の想いが同じ重さで尊重されること。それが、真の意味での「家族のかたち」なのだと、改めて胸に刻みたいものです。