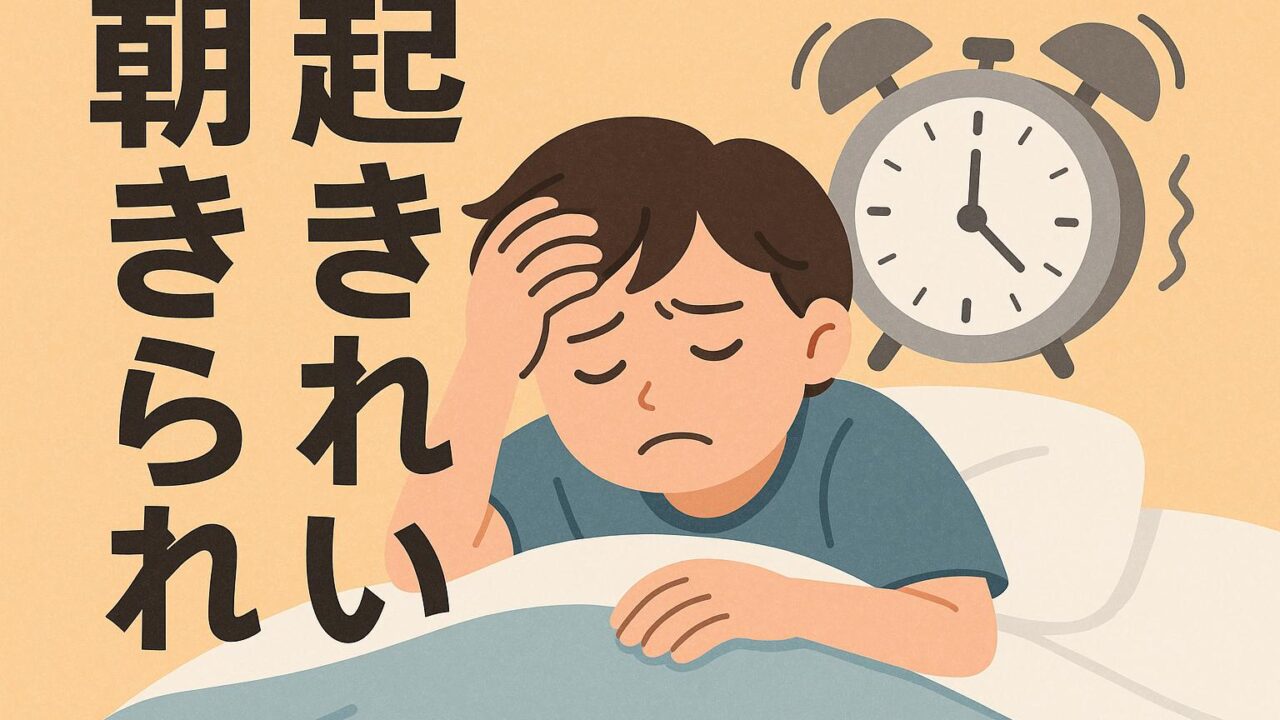「朝起きられない」という悩みを持つ子どもたちがいます。それも単なる寝坊や怠けとは違い、深刻な体調不良や苦痛をともなう症状として起こっていることがあります。最近注目を集めているこの問題は、「起立性調節障害(OD:Orthostatic Dysregulation)」と呼ばれる自律神経系の障害である場合が多く、本人だけでなく周囲の大人たちにとっても理解と対応が求められるテーマです。
この記事では、この「起きられない」障害に悩む子どもたちの現状を紹介しながら、身近にいる保護者や教育関係者にとって理解と協力がどれほど大切かを考えていきたいと思います。
朝起きられないのは「甘え」ではない
「学校へ行きたくないから寝ているのではないか」「夜更かしのせいではないか」「根気が足りないのでは」と感じる方もいるかもしれません。しかし「起立性調節障害」は、医学的に認められたれっきとした疾患で、自律神経の不調により血圧や心拍数の調整がうまくいかず、起床時に立ち上がると気分が悪くなったり、立ちくらみがしたりと日常生活に深刻な影響が出ます。
この障害は主に思春期の子どもが発症しやすい傾向がありますが、子ども自身が自分の体調の異変をうまく言葉にできないことも多く、周囲から「サボっている」「怠けている」と誤解されてしまうケースがあります。このような誤解が、子どもたちの自己肯定感を下げたり、家族関係や学校生活に支障をきたす原因にもなってしまうのです。
病気と向き合う現場の声
実際に、「朝どうしても起きられなくて授業に出ることができない」という子どもたちは、心身の苦しみを抱えながらも何とか日常を送り、「ただの怠け者ではない」ことを周囲に分かってもらいたいと一生懸命に戦っています。
記事では、実際にODを患っている生徒やその保護者、そして彼らを支える医療現場の声が紹介されていました。「なんで起きられないの?」「昨日も休んでたよね?」といった言葉に傷つきながらも、自分なりのペースで回復を目指している子どもたちの姿が印象的です。
こうした子どもたちを受け入れ、理解しようとする学校や地域の存在も少しずつ増えてきています。一部の自治体では、通学が難しい子どもたちのためにオンライン授業の活用や個別に応じた登校支援を行うなど、柔軟な対応が始まっています。
家族の不安と葛藤
また、保護者の立場からすると、「なぜ朝になるとこんなに辛そうなのか」「何か家庭でできることはあるのか」と不安になるのも無理はありません。仕事を休まなければいけなかったり、子どもに対してどう接すればいいのか分からなかったりと、悩みを抱える親御さんも多くいます。
ある母親は、「この病気を知るまで、ただの思春期だと思っていた。けれど、子どもが一番苦しんでいた」と語ります。ODは日によって体調が違ったり、午後になると比較的元気になったりするため、外から見ただけでは病気とは分かりにくく、対応が難しいのです。
心のケアの大切さ
ODによって長期的に学校に行けない状態が続くと、「自分は周りと違う」「社会から取り残されているのではないか」といった不安や孤独感を抱いてしまうことがあります。身体的なサポートはもちろんのこと、メンタルケアの重要性もますます高まっています。
医療機関では、自律神経の働きを整える薬の処方や、生活リズムを整えるためのアドバイス、心理的な支援など多角的なケアが行われています。学校や家庭においても、「できることを大切にしよう」「ゆっくり回復すればいい」といった前向きな声かけが、子どもたちにとって大きな支えになります。
社会全体で支えるために
ODをはじめとしたさまざまな体調不良により、「普通の生活ができない子ども」は決して少数派ではありません。車椅子を見ると物理的な障害だと理解されやすいのと同じように、“見えない障害”も確かに存在しており、私たちがその存在を正しく理解することが、子どもたちの未来を広げる大きな一歩になります。
記事を通じてあらためて実感したのは、「無理に学校に行かせること」よりも「その子の状況を理解し、協力的な環境をつくっていくこと」が何よりも大切だということです。家庭や学校、医療機関、地域社会が連携し、柔軟かつ思いやりのある対応を進めていくことが望まれています。
最後に
子どもたちは、誰も好きで苦しんでいるわけではありません。眠っているように見えて、心も体も大きな負担を抱えています。そのことを少しでも多くの人が理解し、優しさの輪が広がることが求められています。
「起きられない障害」に悩む子どもたちが、自分らしい生活を取り戻し、明るい未来に向かって歩き出せるように。私たち大人ができることから、一歩ずつ始めていきましょう。