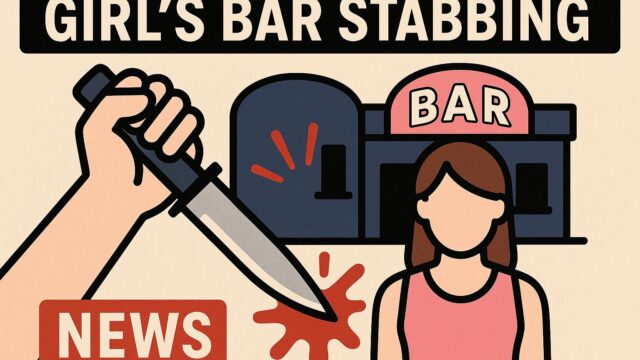長崎の「原爆稲」――平和を願い受け継がれる命の種
長崎の地に、静かにそして力強く受け継がれてきた稲があります。その名も「原爆稲(げんばくいね)」。この稲は、原爆という人類の悲劇の象徴となった土地から芽吹いた、特別な命のバトンです。それはただの農作物ではなく、平和への祈りと、過去に学び未来へと繋ぐ思いが込められた小さな種子なのです。
原爆稲を育て継ぐという尊い営みを続けている一人の男性がいます。84歳の久保山壽一(くぼやま・としかず)さんです。彼の人生は、まさにこの原爆稲と共に歩んできたと言っても過言ではありません。毎年田植えの季節がくると、久保山さんは大切そうに田んぼに足を運び、その小さな苗を畑に植えつけます。その姿は、戦争の悲劇を繰り返させてはならないという静かな宣言のように映ります。
では、「原爆稲」とは何なのでしょうか。
原爆稲の起源は、長崎に投下された原子爆弾にまでさかのぼります。かつて爆心地の近くにあった長崎医科大学(現在の長崎大学)の付属病院に立っていた病棟の瓦礫の中から、一本の稲穂が発見されたと言われています。この稲が成長して実を付けたことに、関係者たちは驚きと希望を抱きました。「あの日、すべてが焼き尽くされた中でも、命は息づこうとしていた。」そのメッセージが込められた原爆稲は、以後、平和の象徴として人々の手によって大切に育てられていくことになります。
久保山さんが原爆稲の存在を知ったのは、偶然訪れた展覧会がきっかけだったといいます。ガラスケースに収められた原爆稲の穂と、その横に添えられた説明文を見た瞬間、胸にこみ上げてくるものがあったと語ります。そして、ただ見て終わるのではなく、行動に移したいという思いにかられた久保山さんは、自ら栽培することを決意します。
以来、40年以上もの間、彼は原爆稲の種を受け継ぎ、毎年田植えと収穫を欠かさずに続けてきました。この原爆稲の育成は、他の稲と比べて特別に難しいというわけではありません。けれども、ただ育てるだけではなく、その背景に込められた意味を見つめながら手間暇をかけることで、稲作業は命と平和をつなぐ行為に昇華されるのです。
久保山さんの田んぼは、決して広くはありません。それでも、毎年思いを込めて小さな苗を一つ一つ植えていく姿は、見る人に深い感動を与えます。時には、地域の子どもたちも田植え体験に訪れます。子どもたちは最初こそ泥に足を取られて笑いながら田んぼに入りますが、次第に真剣な表情へと変わり、命の重みと平和の意味を学んでいきます。
「原爆稲」を次の世代に受け継いでいくこと――それは、単なる伝統行事ではありません。戦争の記憶が風化しつつある今こそ、小さな一粒の稲が語る歴史の重みを、私たちはしっかりと胸に刻まなければならないのです。
久保山さんが言うように、
「この稲はただの植物ではない。あのとき、人間の無知がもたらした悲劇の中でも、生きようとする命があった。そのことを、ひとりでも多くの人に知ってほしい。」
この言葉には、多くの人が忘れてはいけない教訓が込められています。
田んぼは、四季によって様々な表情を見せます。苗が植わり、太陽の光を浴びてすくすくと育っていく姿は、希望そのものです。そして、稲穂が黄金に実ったとき、それを見る久保山さんの目には、どこか懐かしく、切ない光が宿っています。
「自分ができることは小さなことかもしれない。でも、それが誰かの心に火を灯すなら、この稲はきっと力になる。」
長崎の原爆という不幸な出来事、それをただの記録として置き去りにするのではなく、今を生きる私たちの生活の中で考え、感じ、次へと繋ぐために。「原爆稲」はそのための、かけがえのないメッセンジャーであるといえるでしょう。
平和とは、遠い場所にあるものではなく、私たち一人一人の行動の中にあるものです。久保山さんがそうであるように、小さな行動が大きな意味を持ちうるのです。たとえば、こんな話を周囲に伝えることもそうです。あるいは、子どもに絵本で歴史を語ることもまた、平和への立派な歩みです。
この長崎の「原爆稲」は、戦争の惨禍から這い上がった命の象徴です。そして、手渡された命と記憶を、未来へとつなぐ架け橋です。田んぼに立ち、泥にまみれながら稲を植える久保山さんの姿は、静かなる祈りそのものと言えるでしょう。
私たちもまた、その祈りに応えていく必要があるのではないでしょうか。
原爆稲に込められた想いを受け止め、自分なりの形で平和への一歩を踏み出していく。それが、この時代を生きる私たちに与えられた、生きた証のひとつになるのかもしれません。