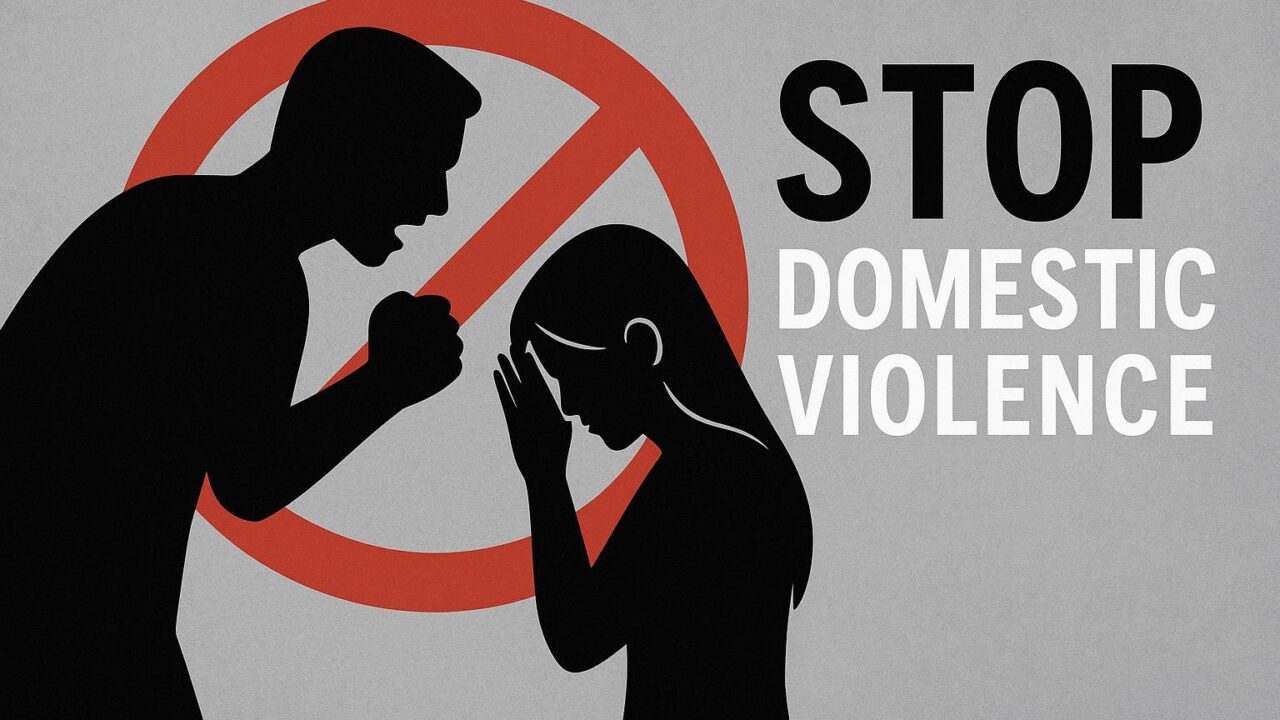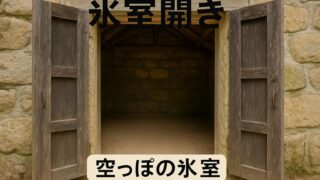交際相手への暴力事件から考える――私たちが向き合うべき「見えない暴力」とその防止策
近年、パートナー間における暴力、いわゆる「ドメスティック・バイオレンス(DV)」が社会問題として大きな注目を集めています。報道によれば、ある男性が交際中の女性との口論の末、胸の骨を折る重傷を負わせたとして逮捕されました。被害女性は約1か月の重傷を負ったとされており、事件の衝撃や背景に多くの人々の関心と懸念が集まっています。
こうしたニュースが伝えられるたびに、「まさかそんなことが自分の身近で起こるわけがない」と思う方も多いかもしれません。しかし、実際にはDVはあらゆる世代、あらゆる背景の人々に起こり得る問題であり、決して他人事ではありません。この記事では、今回報道された事件をきっかけに、交際関係における暴力の実態と、それにどう向き合っていくべきかについて考えていきます。
■ DVは身体的な暴力だけではない
報道された事件では「胸の骨を折る」という身体的暴力が加えられたとされていますが、DVにはさまざまな形があります。日本の法律や啓発活動においても、「暴力」は単に殴る・蹴るといった物理的行為だけを指すものではありません。具体的には以下のような種類があります。
1. 身体的暴力:叩く、蹴る、物を投げつけるなど、直接身体に害を与える行為
2. 精神的暴力:怒鳴る、無視する、侮辱する、脅すといった言葉や態度による支配
3. 性的暴力:同意なしの性行為や、意に反した性的行為の強要
4. 経済的暴力:お金を管理させない、働かせない、生活費を与えないなどの経済的支配
5. 社会的隔離:友人や家族との連絡を妨げる、外出を制限するなど
こうした暴力の中には、外からは見えにくい、証明しづらいものも多く、被害者自身が「これは暴力なんだ」と気づかないまま関係が続いてしまうケースも少なくありません。
■ 暴力の根底にある「支配欲」と「自己正当化」
交際相手への暴力は、「愛情があふれているがゆえに」と誤解されることもありますが、実際にはそうではありません。多くの場合、その根底には「相手を自分の思い通りにしたい」「自分が上に立ちたい」といった支配欲が存在しています。
さらに、加害者は自身の暴力行為に対して「相手が悪かったから」「自分の怒りは正当だ」と自己正当化の論理を持ち出すことがあります。これによって暴力は繰り返され、一時的な謝罪や反省の言葉によって被害者は希望を持たされ、また関係を続けてしまう――こうした「暴力と和解」のサイクルが、DVを長引かせ、深刻化させていくのです。
■ 被害者が声を上げることの難しさ
「被害者なら、なぜもっと早く逃げなかったのか」と思う人もいるかもしれません。しかし、DVの被害者が自らの被害を外部に訴えることは決して簡単なことではありません。前述のとおり、DVが目に見えにくい場合もあり、「自分が悪いのでは?」「大げさにしてはいけない」といった自己否定的な思考にとらわれてしまうこともあります。
また、経済的な依存や住居、子育てといった現実的な事情が、脱出を妨げる大きな要因にもなります。その上、加害者が「謝罪する」「二度としない」と約束し、被害者の無念な気持ちや愛情につけこむことも多いため、なかなか関係を断ち切ることができなくなってしまいます。
■ 周囲の理解と支援がカギを握る
被害者が暴力の連鎖から解放されるためには、社会全体の理解と支援が不可欠です。家族、友人、職場の同僚、そして地域社会が、DVのサインに気づき、適切な声かけや支援につながる対応を取ることが重要です。
たとえば以下のような行動が、被害者の救済につながる可能性があります。
– パートナーとの関係で悩んでいるように見える友人に「いつでも話を聞くよ」と声をかける
– 身体に不自然なアザやけがを繰り返す人に、心配であることを伝える
– 周囲で叫び声や物音など不自然な音が聞こえる場合に、ためらわず警察・行政機関へ通報する
何より大切なのは、被害者を責めないこと。「自分から離れなかったから悪い」という考えは間違いであり、そのような視点ではなく「一緒にどうすれば安全で安心な環境に戻れるのか」を共に考える姿勢が求められます。
■ 相談窓口や支援制度を知る
日本には、DV被害に遭った人のための相談窓口が用意されています。全国の配偶者暴力相談支援センターや、警察、そして公的機関の窓口が支援にあたっています。電話相談や面談によって、今置かれている状況の中でどのような支援が受けられるかが丁寧に案内されます。
また、民間のシェルターやNPO法人なども被害者の避難や就労支援、精神的なケアなどを行っています。大切なのは「1人で抱え込まず、まずは誰かに話すこと」。話すことで状況が整理され、そして支援の選択肢が見えてくることも少なくありません。
■ 私たち一人ひとりにできること
DVは個人の中だけで起きている問題ではなく、社会全体の理解と行動によって防止・解決へとつながります。こうしたニュース記事を「怖いことだ」と捉えるだけで終わらせるのではなく、「自分の周囲でも起こり得る」「自分の態度や行動が被害者の支えになるかもしれない」と意識することが第一歩です。
私たちは皆、誰かのパートナーであったり、同僚であったり、親友であったりします。人を支える力を持っていると同時に、無関心が誰かをさらに孤立させてしまうこともあるのです。互いに尊重し合い、暴力を許容しない社会をつくるためにも、小さな気づきと声かけを大切にしたいものです。
■ まとめ
今回の事件を通じて、DVの現実やその見えにくさ、そして被害者が抱える葛藤に思いをはせることは、非常に重要です。個人の自由と尊厳が守られるべき交際関係において、暴力が容認される余地はありません。
報道をただの「事件」として受け止めるのではなく、今の社会における私たち一人ひとりの役割や責任を考え直す機会にしていきましょう。そして、誰もが安心して過ごせる人間関係と社会を築いていくことが、未来の悲劇を防ぐ一歩になるのではないでしょうか。