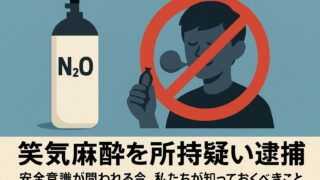※本記事は極めてショッキングな事件内容を含んでいますが、社会的に重要なテーマであるため、慎重かつ誠実な姿勢で執筆しております。被害者の尊厳と読者の感情に配慮し、適切な表現で説明するよう努めています。
—
【子どもを守るということ——深刻な性被害事件から私たちが学ぶべきこと】
私たちが想像する以上に、子どもの身の回りは危険であふれています。ましてや、それが信頼関係に基づくべき人間関係のなかで行われたとしたら——今回、報道により明らかになった事件は、そのような信じがたい現実を突きつけました。
ある男性が、自らの娘である幼い7歳の女児に対して、性暴力を加えた上、その様子を動画に撮影し、さらにはその動画をSNSで知り合った人物に共有していたという、極めて悪質かつ深刻な事件が裁判で争われ、実刑判決が言い渡されました。
司法はこの事件を、「誠に悪質で、かけがえのない人格形成期にある被害者の心身に深刻な影響を与えた」として、厳しく非難しました。これは、単なる家庭内の犯罪ではなく、社会全体が責任を持って見つめ直し、防止に向けて行動するべき象徴的な事例です。
では、私たちはこのような事件から何を学べるのでしょうか? そして、加害や被害を事前に防ぐために、社会として、家庭として、個人として、どのようなことを考えていくべきなのでしょうか?
—
■ 家庭という「安全圏」の崩壊
一般的に、子どもにとって家庭というのは、もっとも安らげる場所であり、成長の土台となる場所とされています。親は子どもの味方であり、信頼できる存在として機能することが求められています。しかし、この事件では、その「安全」とされるべき空間を利用して、重大な人権侵害が行われてしまいました。
家庭内での性暴力は、被害が表面化しにくいことが特徴です。「誰にも言えない」「恥ずかしい」「家族を失いたくない」などの理由から、被害者が声を上げることが難しく、それを利用する形で加害が継続するという負のスパイラルが存在します。
だからこそ、社会全体として「家庭だから安心だ」といった価値観を更新し、たとえ家庭の中であっても、おかしなことは「おかしい」と伝え、周囲が子どもを見守り、寄り添う姿勢が求められるのです。
—
■ デジタル社会と新たな拡散リスク
今回の事件では、加害者がその様子を動画としてSNSを介して共有するという、インターネットを介した二次的加害が行われました。これもまた、現代特有の深刻な問題といえます。
かつては秘匿されていた家庭内での性被害も、今では写真や動画として記録され、それが拡散・保存されていくという、被害が永続化する仕組みができあがってしまっています。そして、それは一度出回ると消し去ることがほぼ不可能で、被害者に「終わりのない苦しみ」を与えてしまうことになります。
インターネットに接続する技術は格段に向上し、それにともない多くの恩恵もありますが、今回のように悪用されうる危険があることも事実です。インターネットの匿名性や広域性が、時に人の道徳心を麻痺させ、加害を加速させる危険性がそこにはあります。
—
■ 壊された幼い心と、私たちの責任
今回の事件で最も心を痛めるのは、被害者である女の子が、これから成長していく大切な時期に、深い心の傷を負ってしまったことです。裁判でも、「人格形成に極めて深刻な影響を与えた」と言われたように、性暴力の傷は身体的なものだけでなく、精神的にも計り知れないダメージを残します。
これから彼女が社会と関わり、自分自身を大切にし、他者と信頼を育んでいくプロセスには、並々ならぬ困難があるかもしれません。心の傷は見えにくく、周囲から理解されず、孤立してしまうリスクもあります。
だからこそ、私たち大人一人ひとりが、周囲の子どもへ意識的に「安全」を届ける必要があるのです。子どもの話に耳を傾ける、違和感を感じたら勇気を出して踏み出す、子どもが安心して助けを求められる環境を整える——そのことが、次なる被害を未然に防ぐ、小さくも確実な一歩になるのです。
—
■ 子どもたちの声を守る社会へ
この事件は、司法により厳しい判決が下されました。大人の責任として当然のことです。しかし、ただ加害者を罰すればそれで終わり、という問題ではありません。
私たちは常に「どうすれば次の子どもが同じ目に遭わずにすむのか」を真剣に考える責任があります。教育の場、家庭環境、法制度、SNSの規制など、多面的な視点で改善すべき部分は多くあります。そして、声を上げられない子どもたちの代わりに、周囲の大人が声となり、壁となり、時に盾となることが必要です。
また、周囲に加害予兆を垣間見るような言動をする人がいれば、早い段階で介入し、専門機関に相談するような連携も肝要です。「疑ってはいけない」という迷いよりも、「守られるべき命がある」という視点を最優先にしなくてはなりません。
—
■ 最後に:子どもが笑って過ごせる世の中に
子どもが安心して過ごせる社会は、大人にとっても健全で、未来に希望が持てる社会です。そして、その土台を作るのは一部の専門家や行政だけではなく、私たち一人ひとりの意識と行動です。
人間は誰もが生まれながらにして尊厳があり、大人であれ子どもであれ、その尊厳を守ることは社会の最も基本的な責務です。子どもたちの笑顔を守ることは、人間としての最も大切な使命のひとつであると言っても過言ではありません。
今後、このような痛ましい事件が再び起きないことを切に願うとともに、私たち一人ひとりが、日々の生活の中で「子どもを守る」という視点を持ち続けることが、社会をより良くしていく大切な一歩になるはずです。