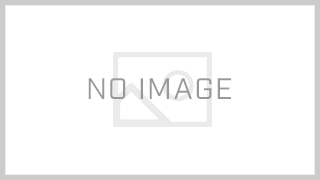2024年6月、プロ野球界を静かに、しかし確かな存在感をもって去っていった一人の投手がいる。日本ハム・加藤貴之投手(32歳)が、左肘の張りにより登録を抹消され、今季から導入された新ルール「再登録まで10日→15日」の影響を受けて、オールスター出場を辞退することとなった。このニュースは一見、故障者の出場辞退という日常的な情報かもしれない。しかし、日本ハムの加藤投手にとっては、これが単なる”辞退”ではなく、これまでのキャリアと誠実な投球スタイルを象徴する出来事でもあった。
加藤貴之投手は、1992年6月3日、千葉県に生まれた。身長177cm、体重85kgの体躯から繰り出される球は、150キロ台の豪速球ではない。しかし彼の真骨頂はその「制球力」である。「コントロールの加藤」「四球を出さない技巧派左腕」として知られ、徹底して投球の精度を追求してきた。駒澤大学を卒業後の2015年、ドラフト2位で北海道日本ハムファイターズに入団してからというもの、彼は常にチームにとって信頼できる投手であり続けた。
加藤の持ち味は何といっても抜群の安定感だ。特筆すべきは、その抜群の制球。“無四球試合”はもはや彼の代名詞ともいえ、この点で彼の名はプロ野球界にしっかりと刻まれている。2023年には、無四球率0.55という驚異的な記録を叩き出し、歴代2位(1950年以降ではダントツの1位)という偉業を成し遂げた。すなわち、四死球を全くと言っていいほど出さず、試合の流れを自ら壊さない。「試合をつくれる投手」。それが加藤貴之なのだ。
2022年にはプロ入り後最多となる10勝を挙げた。開幕から長期にわたりローテーションを守り、しかも与四球が極端に少ないため、攻撃にもリズムが生まれる。打線が沈むときでも粘投し続ける姿は、チームメイトからも厚い信頼を得てきた。まさしく、チームの“縁の下の力持ち”を地で行く男である。
その彼が、今回、オールスター出場を辞退した。理由は、6月23日のオリックス戦で左肘の張りを訴え、登録抹消となったこと。新たに導入されたルール「故障者の一軍再登録までの期間が10日から15日へ」が適用され、これにより7月23日(火)札幌ドームのオールスターには間に合わなくなった。
本人にとってもファンにとっても、これは残念な知らせだった。なぜなら今回のオールスター出場は、加藤にとってキャリア初の快挙だったからだ。日本ハムからは、他に伊藤大海、万波中正、松本剛という3選手が選出されているが、加藤の選出こそが一番のサプライズだったと言える。
彼の投球成績を見れば、今年もすでに開幕から8試合に登板し、防御率2.86。被本塁打0という事実が、彼の“華やかではないが確実な実力”を如実に表している。その中で、オールスターの投票が始まって以降、多くのファンや関係者が、「この制球力の高さを全国に見せるべきだ」と 推していたのだ。それだけに、辞退の報が伝えられたとき、多くのファンが「ようやく評価され始めたのに…」「彼にとって最初で最後の晴れ舞台だったかもしれない」と落胆した。
加えて、加藤貴之の辞退は、今回から試験的に導入されたルールが実戦でどう影響を及ぼすかを示す事例にもなった。これまでは、最短10日で再登録可能だったため、オールスターを見越した調整も効いたが、15日となると選手にとってはかなり厳しい。このルールによって、加藤のように“ギリギリ間に合いそう”なケースは事前辞退を余儀なくされる。
今後、このルール運用については議論の的になる可能性もあるが、決して悪いルールではない。むしろ、軽傷の状態で無理に試合に出場させず、しっかり治療に専念させるためのルールと言える。加藤本人も「チームにとっても、自分にとっても、これからのシーズンがより大事」とコメントしており、あくまで前向きな辞退であることが伺える。
こうして加藤貴之は、惜しまれつつもオールスターの舞台から姿を消すことになった。しかし、彼の“技巧派左腕”としての美学、そして「派手じゃなくても強い野球がある」というスタイルは、多くのプロ野球ファンに深く印象を残した。プロ野球という世界において“速球派”や“豪快な三振”に比べて“制球力”は地味に見えるかもしれない。だが、だからこそ、加藤のような存在がより光を放つ。
これからも彼は、目立たないけれど確実に、北海道のマウンドに立ち続けることだろう。オールスターという特別な“1試合”には出場できなかったかもしれない。しかし彼が見せてきた“毎試合の堅実な積み重ね”こそが、プロという職業の本質なのではないだろうか。多くの若手投手たちが彼の背中を見て、次なる時代をつくっていく。そのとき、加藤貴之の名は、まさに“手本”として語り継がれていくに違いない。
そして来年こそ、再びオールスターの扉が彼の前に開かれることを、誰もが願っている。